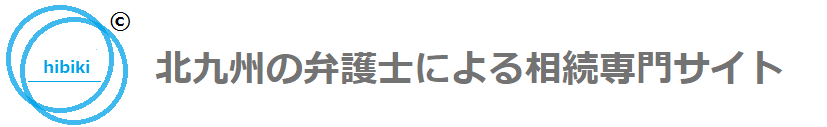民法における原則の一つに、自力救済の禁止の原則という原則があります。
自力救済を行う行為は、自己救済ともいいます。
この自力救済は、中核的には、民法において議論される原則ですが、刑法(犯罪被害を回復するなどの刑事的な場面)でも登場します。
刑法においては主として「自救行為」という用語が使用されることが多いかもしれません。
自力救済の意味
典型例としては、たとえば、窃取された窃盗品を取り返す、というような行為が挙げられます。
ただ、民法上、自力救済というときは、もっと広く、司法手続によらず、自分の実力で自己の権利を実現することを指します。
たとえば、売買契約をした売主が、相手の自宅まで行って相手が払えないと言っているのに、家に置いてあった現金を売買代金として取ってくる、といったような行為も自力救済の一つといえます。
自力救済の歴史と司法制度
前近代では、自力救済は広く行われていました。
今日では、自力救済は、原則として禁止されています。「やられたらやり返す倍返しだ!」なんてもってのほかです。
前近代社会において(復讐まで容認された社会)
今日のように整備された司法制度が確立していなかった室町時代や鎌倉時代においては、自らの権利や利益を自らの力で守る、自力救済が権利実現のための重要な手段となっていました。
刑事的な問題ではありますが、かたき討ちなどが容認されていた時代もあります。
「やられたら、やり返す」、これも自力救済の一種に位置付けることが可能です。
近代以降の社会において(実力行使が禁止された社会)
現在の民法では、自力救済の禁止が当然のように原則となっています。
また、刑法においても、正当防衛や緊急避難といった防衛行為や避難行為までは認められるものの、犯罪が完全に終了した後になって、報復行為を行うことはやはり禁止されます。
近代社会秩序、現代社会秩序において、実力行使によって、自らの被害を回復(権利を実現)する自力救済は原則として禁止されるようになったのです。
ただ、蛇足ではありますが、近代化・現代化が進んだ先進国の中でも、アメリカでは、自力救済を是とする考え方が根強いと言われています。
なぜ自力救済を禁止した?認められるべきでは?
自力救済を許容すると実力が物を言う社会になる
侵害行為に対する自力救済を許容すれば、どういう社会になるでしょうか。
間違いなく、力の強い者、実力行使できる者のみが権利を実現できる社会となります。
これでは社会秩序が維持できません。
高校生にも勝てないであろう非力な私も、実力が物を言う社会では困ります。やられても、やり返せません。
間違いが生じやすい
また、自力救済を許容すると、第三者による慎重な判断無く、救済行為が行われるため、真実に反して権利行使がされるおそれが大きくなります。
被害者や権利者の思い込みや誤解によって本来加害者でない者が責められることになりかねない、という訳です。
そこで、司法制度が整備された近代社会においては、権利の実現や被害の回復は、中立・公平な司法の慎重な手続に則り、国家権力により実現することとされています。
正当防衛との違い
自力救済と正当防衛とは、自らの権利に対する侵害につき、被害者が自らの権利を守ろう、確保しようとしている点で似ています。
しかし、正当防衛は、今まさに行われている権利侵害行為に対する防衛行為であるのに対し、自力救済は、権利侵害行為が終わった後に、自らその救済を図ろうとする行為である点に違いがあります。
そして、正当防衛と言える場合には、原則として当該防衛行為は容認されます。自力救済のように、「禁止」が原則にはなりません(参照民法720条1項本文)。
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
自力救済に関する条文
ただし手掛かりとなる規定はあります。民法200条1項や414条1項本文です。
意外なことに、民法には、自力救済の禁止を定めた直接の規定はありません。
もっとも、民法200条1項や民法414条1項本文が手掛かりになります。
両規定は、被害の回復や権利の実現について、被害者や権利者が、訴えにより、被害を回復したり、権利を実現したりすることができると定めています。
被害回復や権利の実現について、裁判所への訴えによることが基本とされているのです。
やられたら、裁判でやり返そう、民法が想定しているのは、そういう大人な社会です。
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
自力救済の禁止の原則の弊害・デメリット
自転車の取り戻し、違法駐車の是正、権利行使、賃貸物件の明渡しなどの場面を想定してみます。
いずれの場合も、自分の権利を実現する、というだけなのに、そのための手段が非常にめんどうです。
上記の通り、自力救済の禁止の原則は、社会の秩序維持に主眼があるわけですが、法がこの原則を採用することによって生じる弊害・デメリットもあります。
それは、法が定める手続をとらないと権利が実現しないということです。
その意味は権利の実現に経済的・時間的コストがかかることを意味します。
自力救済と自転車の取り戻し
あなたの自転車が盗まれたとします。
自転車が盗まれて困り果てていたところ、偶然、自分の自転車を駅の駐輪場で見つけた。鍵もかかっていない。
このケース、普通の人は、その場で取り返したくなると思います。しかし、自力救済禁止の原則を貫徹すればそれもできません。
これを取り返すには裁判をしてください、ということになります。
手間暇、費用を考えると、裁判なんてとても現実的ではなく、かといって、これを勝手に持っていくと民事でも負け(上記、民法200条1項)、刑事でも窃盗や逸失物横領に問われる可能性がある。
お察しの通り、自転車を取り戻すだけなのに、非常に面倒です。
自力救済と違法駐車
あなたの土地に違法駐車がなされている場合、相当のお人好しでない限り、当然、排除したいはずですが、自力救済は禁止です。
そのため、法律上は、裁判して、所有者に撤去を要求することになりますが、そもそも、敷地に止められた車が誰の車かも当初わからない。そこから調べなければならない。
裁判といっても手続は難しい、弁護士に依頼するにしても、費用が必要。
しかも、その費用はあなたの負担と言われます。やはり非常に面倒なことになります。
自力救済と債権行使(権利行使)
権利行使ですら、制約を受けます。
たとえば、ある商品をネットオークションで1万円で売ったとします。
商品発送して、買主が商品を確認後、代金を払う契約だったとします。
このケースにおいて、売主が商品を買主の住所まで送ったのは良いものの、買主からはいつまで待っても代金が振り込まれない。
このケースにおいて、売主は、送り先である買主の住所は分かるので、押しかけて取り立てたいところですが、自力救済の禁止の原則の下では、無理やり現金を取ってくるのはもちろん違法。
買主の自宅まで行っても、払わない、と言われればそれまで。裁判をしてください、ということになる。
1万円のためだけに、裁判しますか?その手間とコスト、掛けられますか?非常に面倒です。通常はできません。
賃貸借物権の明け渡し
賃貸の場面でももちろん自力救済は原則禁止です。
借主が家主を払わないからと言って、貸主・オーナーは、司法手続によらず、無理やり借主を追い出したり、使わせないようにするために、ドアのカギを勝手に変えてしまうなどすることはできません。
借主が賃貸物件から出ていかない場合、家主・オーナーは、建物明け渡しを求めて訴訟提起し、強制執行をかける、という手段をとらざるをえないことになります。
それにはもちろん、手間・コストがかかるわけで、やはり面倒です。
自力救済禁止の原則の例外
以上、自力救済の禁止の原則について見てきました。社会秩序維持というメリットはあるものの、弊害もあります。
そして、上記のような弊害を緩和するには、どうしても一定の例外を許容することが必要です。
自力救済について例外を全く認めない、という解釈は現行の司法制度の下では成り立ちません。
そこで、次に、原則に対する「例外」について見ていきます。
自己救済を原則禁止した最高裁判決
昭和40年12月7日の非常に有名な最高裁判決です。
「私力の行使は、原則として法の禁止するところではあるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」
この判決は、要するに、裁判等を利用するのでは、権利侵害に対抗することがまずできないという場合であって、緊急やむを得ない事情がある、といえるときだけ、自力救済が認められる、とした判決です。
判例法理上、一定の例外は認められたものの、自己救済が許容されるための条件設定は、極めて厳しく、この条件の下で自力救済が認められるのは稀なケースに限られます。
地方裁判所の判決
そこでは最高裁の求める条件を満たすか否かが争われます。
肯定例・否定例ともに存在します。
自力救済が否定されたケース 東京地方裁判所平成16年6月2日判決
東京地裁平成16年6月2日判決は、建物明け渡しに関し、違法な自力救済にあたると判断した判決です。
このケースは、事務所兼倉庫を賃借していたオーナーが、賃料不払による契約の解除後、たまたま賃借不動産に居合わせた借主の従業員立会の下で、賃借不動産のカギを取り換えたというケースです。
借主の代表者は鍵の交換に承諾も容認もしていなかったと認定されています。
このケースにおいて、東京地方裁判所は、鍵の取り換えが違法な自力救済に当たると判断しています。ここでは自力救済禁止の原則の本旨が貫かれています。
自力救済が認められたケース 昭和63年2月4日横浜地方裁判所判決
他方、昭和63年2月4日横浜地方裁判所判決は、自力救済を肯定した事案です。
このケースは、をある自動車の所有者が、車を移動するように再三にわたって督促されたにもかかわらず、人の不動産の前に車を3ヶ月間置きっぱなしにしたというケースです。
住人が車を処分したのに対し、車の所有者が違法である旨主張すべく損害賠償請求訴訟を提起しました。
横浜地方裁判所は、当該ケースにおいて、上記最高裁にいう「やむを得ない特別の事情」があるとして、損害賠償請求を認めませんでした。
この裁判例は、自力救済が違法とされなかった極めてまれなケースの一つとして、有名になったケースです。(ただ、司法手続に則ることができなかったか、疑問なしとしないとの見解もあり得るところです)。
ビジネスにおいて
ビジネスでも自力救済が機能
自力救済禁止の原則が一般秩序の維持に役に立っているのは間違いありません。
ビジネスの面でも同様であり、実力が強い者が勝つ社会であれば、そもそも全うなビジネスは成り立ちません。
腕力の強い者を集めた会社や武器を扱う会社が勝利するということになってしまいます
このような社会は、自力救済禁止の原則によって排除されます。
禁止だからこそ工夫が重要
しかし、他方で、上記で見た各事例でも明らかなように、自力救済の禁止の原則の制度の下では、権利の実現・回復に手続的なコストを要することになります。
また、自己救済が認められるケースは例外的な事例・場面に限られます。
そのため、権利をどのように実現するのか、そのコストや方法については、常にビジネスにおいて念頭に置いておかなければなりません。
このコストを回避するためには、たとえば、取引の相手に先に義務を履行させる(売買において、売主の立場でいえば、相手に代金を先払いさせる)等の工夫、モデルの構築が重要となります。