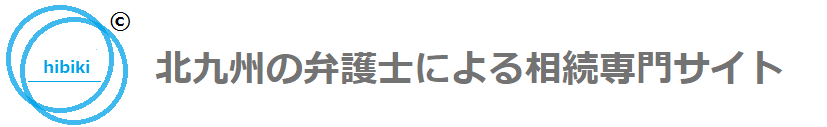民法において、瑕疵ある意思表示に位置付けられるものの一つが、民法96条第1項に定められた強迫です。
詐欺と並んで、意思表示の取消事由となっています。
今回は、その意味や要件、効果について解説します。
民法96条1項
取り消された場合、意思表示が初めからなかったことになります。
条文はいたってシンプルです。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
「取り消すことができる」というのは、強迫をされた者が、契約などにかかる意思表示をなかったことにできる、という意味です。
取消しがなされないと、意思表示は有効なまま維持されますが、取消がなされることによって、意思表示が初めに遡ってなかったことになります。
取消がなされることにより、たとえば「買う」という意思表示により成立した契約を無効とすることができます。
ここで関連記事を紹介!
今回は、強迫について解説しますが、詐欺を含めた民法96条全般については、次のページでも解説しています。
併せて読んでいただくと理解が深まると思いますので、ぜひご一度参照いただけますと幸いです。
強迫による意思表示の取消の要件
- 強迫がなされたこと
- これによって相手が畏怖したこと
- 当該畏怖に基づいて意思表示がなされたこと
以下、それぞれ要件を見ていきます。
①強迫がなされたこと
民法96条にいう「強迫」とは、人に意思表示をさせようとする害悪の告知を指します。
かかる告知がなされた場合、「強迫がなされた」の要件を満たします。
この点、刑法上の「脅迫」は、人に義務のないことを行わせようとする害悪の告知を指します。
他方、民法における「強迫」とは、人に意思表示をさせようとする害悪の告知を指します。
害悪の告知というのは、その人にとって有害になることを告げる行為です。
不当な利得を得る目的でなされる限り、告訴などの正当な権利行使をする旨告げることも強迫に該当しえます。
黙示の強迫の例
害悪の告知は、明示でも黙示でも構いません。黙示での告知というのは、「言葉に出さずに、害悪を伝える」ことを指します。
黙示の強迫の例として、教科書事例ですが、たとえば、「暴行を加えたうえで、金を指さす」といった行為が考えられます。
その他、「狭い部屋で、複数人が一人を取り囲んだうえで、不当な内容が記載された念書等をその一人に交付する」などの例が考え得ます。
これらの行為は、言葉でこそ害悪の告知がなされていませんが、立派に相手を畏怖させるものです。
これらの行為は、刑法上はもちろん、民法上も違法であり、このような行為によってなされた意思表示は民法96条により取消の対象となり得ます。
強迫の故意
強迫がなされたといえるためには、加害者に強迫の故意があったことが必要です。
たとえば、お金などもらう気はなかったのに、むしゃくしゃして相手に暴言を吐いたら、たまたま相手がお金を支払う、と言ってきた場合はどうでしょうか。
この場合、加害者は、暴言を吐いた当時、相手にお金を支払わせよう(有償で契約をさせよう)とする故意はないので、「強迫がなされた」の要件は満たしません。
「強迫がなされた」といえるためには、加害者に、害悪の告知によって相手を畏怖させ、かつ、その畏怖によって意思表示をさせようとする故意があったといえることまでが必要となります。
相手方からすれば、加害者が上記故意を有していたことの立証のハードルが高い、と言う場合が少なくありません。
強迫がなかなか事例として裁判などに出てこない理由の一つでもあります。
なお、この点に関連するものとして注目されるのが、消費者契約法4条3項です。
同規定は、消費者契約に限り、不退去等に基づく困惑によって消費者が意思表示をした場合につき、事業者側の「故意」を問わず、取消の対象となりうる旨、規定しています。
消費者からすれば、この消費者契約法の規定は、事業者側の故意を立証するハードルを下げる意味合いをも有するものといえます。
②これによって相手が畏怖したこと
要は、害悪の告知で怖くなった、びびったことが必要となります。
強迫による取消が認められるには、上記の害悪の告知によって、その相手方が畏怖した(怖くなった)と言えることが必要です。
害悪の告知があったものの、「全く怖くはなかった、だけど、なんか哀れに感じて財布を渡した」、といったケースでは、害悪の告知で相手方が畏怖していないので、民法96条1項の要件は満たしません。
③当該畏怖に基づいて意思表示がなされたこと
要は因果関係が必要。
強迫取消が認められるためには、強迫行為があり、それによって相手が畏怖し、畏怖に基づいて意思表示がなされた、という因果経過が必要です。
害悪の告知によって、いったん怖くなったけど、その後、畏怖状態から脱した上で、意思表示に至った場合はどうでしょうか。
この場合は、害悪の告知による畏怖に基づいて意思表示をしたとはいえませんので、やはり民法96条の要件は満たしません。
以上、3つの要件を見てきましたが、第三者によって強迫がなされた場合の要件も同様に考えます。
第三者たるAさんが①害悪を告知し、②これにより、Bさんが畏怖して、③当該畏怖に基づきCさんに意思表示をしたという場合、BさんはCさんに対する意思表示を取り消せます。
強迫により意思表示がなされた場合の効果
強迫による意思表示は瑕疵ある意思表示として、取消の対象となります。実際に取り消された場合、意思表示は、初めに遡って効力を失います(無効になります。)
ただ、ステップアップレベルですが、いくつか注意しなければならない点がありますので、以下で若干補足します。
取消前の第三者・取消後の第三者という議論です。
ただし、これは、法律の試験等を見据えると重要な論点だけど、実務ではそこまで重要でもないという論点の典型です。
難しいという方は、ひとまずは強迫⇒取消というイメージを作っておくことが先決ですので、読み飛ばして頂いても構いません。
取消前の第三者
結論から言うと、強迫における取消前の第三者は保護されません。
たとえば、Aさんが強迫されて不動産をBさんに売った後、Bさんへの売却の意思表示を取り消す前に、BさんがCさんに不動産を転売してしまったというケースが問題となります。ここでは、Cさんが取消前の第三者です。
この場合、Aさんは、自分の意思表示が取り消された(無効になった)ことを理由にCさんに、不動産を返せと言えるでしょうか。第三者たるCさん保護の必要性はないでしょうか。
詐欺の場合、善意無過失の第三者は保護される
この点に関し、民法96条3項は、「詐欺」取消前に現れた第三者についての規定を置いています。
詐欺の場合、取消前の第三者が善意・無過失であれば、当該第三者は保護されます。
上記の例で言えば、Cさんは善意・無過失であれば、不動産を返還する必要はありません。
強迫の場合、第三者保護規定がない
しかし、同項は、あくまで詐欺に関する規定なので、強迫には適用できません。
そのため、強迫取消前の第三者は、善意・無過失でも保護の対象にはなりえません。
したがって、上記例では、Aは取消の効果をCに主張して不動産の所有権が自分にあることを主張できます。
Cさんは不動産を返さなければなりません。
なお、動産については、要件を満たす限り即時取得の成立を認める見解が有力ではあります。
先の例が動産だった場合、Cさんに即時取得が成立すれば、Cがさん保護されます
取消後の第三者
判例に従えば、この場合、対抗要件具備の先後で勝者が決まります。
たとえば、Bさんに強迫されたAさんがBさんに不動産を譲渡して、不動産の登記名義を移転した後、Bさんへの不動産譲渡の意思表示を取り消したとします。
ところが、Bさんが、Aさんの取消の意思表示の後に、不動産名義をAに戻す前にCさんにさらに不動産を譲渡したとします。
ここでCさんが、取消後の第三者になります。
問題の所在
このケースにおいて、AさんのBさんへの譲渡の意思表示が取消により無効となる場合、Cさんは無権利者たるBさんから不動産を譲り受けたものにすぎません。
しかし、常にこのように解してAさんが保護されるとすると、あまりにCさんの保護に欠ける結果を生みます。
そこで、Cさんを保護する方途ないしAさんとCさんの優劣をどのように考えればよいのかが民法上の議論となります。ここが問題の所在です。
民法94条2項類推適用説
この点につき、学説上は、民法94条2項を類推適用して、Cを保護しようとする考え方が有力です。
この見解は、登記の外観を信じたCさんを保護しようとする見解です。
Cさんが、Bさんのところにある登記の外観を信じて取引に入った場合、CさんはAさんに優先する(所有権を取得できる)と考えます。それ以外の場合はAさんが勝つと考えます。
判例は対抗関係に立つ
他方、判例は94条2項類推適用説を採用していません。対抗問題として処理します。
判例の基本的な立場からすると、AさんとCさんとは、相互に対抗関係に立つと解されます。復帰的物権変動というやつです。
この判例の立場に立つ場合、AさんとCさんとでは、先に登記を具備した方が不動産の所有権を取得し得るということになります。
したがって、もしCさんが登記を具備していればCさんが確定的に所有権を取得しますし、Aさんが登記を先に具備したら、Aさんに確定的に所有権が戻ることになります。
ここで関連記事を紹介!
上記に出てきた民法94条2項の類推適用は、権利者によって登記上の外観が作出されている、あるいはこれと同等と評価できる場合に、しばしば用いられる法理です。
この点については、次の記事で解説していますので、ぜひ一度ご参照ください。
もうひとつ関連記事を紹介!
正直、民法177条を勉強していないと、上記学説と判例の対立の意味合いは分からないと思います。
民法177条については次の記事で紹介しています。
一度ご参照いただければ幸いです。