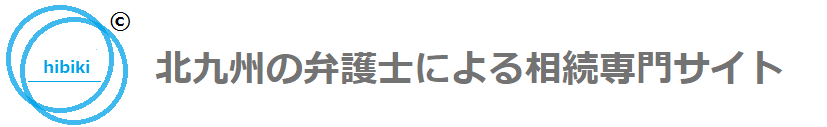今回のテーマは意思能力です。
民法の最初のほうに出てくるテーマですが、意思能力という概念自体、意外と奥行きのある概念です。
今回は少しでもその奥行きを感じていただければと思っています。
民法改正と意思能力
さた、民法改正により、意思能力を欠く者が行った法律行為につき、条文が新設されました。
条文から確認しましょう。(ちなみに条文の場所は民法3条の2とされていますが、個人的には民法第5章の「法律行為」のところに規定したほうが体系的だったのではないかと思います(ブログカテゴリーとしては、「意思表示・法律行為」に分類しました。)。)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
意思能力を欠く場合の無効の意味
この規定は、意思表示をした際、意思能力を有しなかった行為は、無効であるという判例法理を明文化したものと言われます。
また、ここでいう無効というのは、片面的無効(表意者側は無効を主張できるが、相手方においてその無効を主張できない)であると理解されています。誰からでも無効を主張できる、というわけではありません。
その意味で、この意思能力を欠く場合の効果は、取消しに類似するわけですが、改正法では、「無効」の用語が採用されました。
無効と取消等の違いについて、無効を車の鍵のかけ忘れ、取り消しを車の半ドアに例えて解説した記事です。一読いただけると、原則的な無効の意義と取り消しとの違いをご理解いただけると思います。
無効とされる場合の返還の範囲
また契約が無効とされる場合、無効とされた法律行為に基づいて給付を受けたものがあれば、それは、相手に返還しなければなりません。
受け取ったものをそのままにしておく法律上の根拠がないことになるからです。
そして、その範囲については、民法第121条の2が定めています。この点については次の関連記事をご参照ください。
相手に返還すべき対象については、こちらの記事で解説しています。ぜひご参照いただければ幸いです。現存利益の時的基準点などについても考察しています。
意思能力とは
意思能力とは、自分の行為の結果を弁識し、判断することのできる能力を指します。
概念を理解するうえで重要なポイントは、この意思能力は精神的な判断能力(精神能力)である、という点です。
この意思能力を欠いてなされた法律行為は、上記のとおり無効とされます。
表意者側が無効を主張する場合、法律上の効果が発生しないということです。
意思能力は精神的な判断能力である。
上記のとおり、意思能力は精神的な判断能力そのものです。ここが権利能力や行為能力とは異なります。
普段生活していて、自分の「精神能力」を意識することは多くないため、理解が難しいかもしれませんが、たとえば、今、あなたが頭の中でこのブログの記事を理解しようとしている脳の働き、これが精神能力です。
わたしのほうは、精神能力を説明するための例えにどんなものがあるかを頭の中で考えながら、記事を書いていますが、この頭の働きも精神能力の一つです。
もっと言えば、頭の中でものを考える力、と理解するのが端的かもしれません。以下、いくつか、意思能力が欠ける場合を例に、「精神能力」についての理解を深めましょう。
これが意思能力を具体的に理解する上での近道です。
泥酔と意思能力
この精神能力は、個々人の置かれた環境によって大きく左右されます。たとえば、お酒を飲んで泥酔しているとき、考える力は大きく減殺されますよね。
場合によっては、考える力がもう無い、という状況になることもある。
このように、お酒によって、泥酔し、考える力が無くなった、という場合、自分の行為によって何が起きるのか、その結果を理解し、その上で、行動をすべきか否か判断することができなくなります。
これが意思能力を欠いた状態です。
ちなみに、ここでは精神能力を欠いた状態につき、泥酔を例に挙げましたが、医師から処方された内服薬の副作用として意識が混濁したような場合もその例にあげることが可能です。
重度の認知症などの精神疾患と意思能力
また、意思能力を欠く場合としてしばしば挙げられるもう一つの例が、重度の精神疾患です(厳密にはそのうちの一部)。
重度の精神疾患がある状態というのを体験したことのない私は、具体的に想像することはできませんが、ものの本によれば、精神疾患によって、自分の行為の結果を認識しえない状態というのが存在します。
たとえば、重度のアルツハイマー型認知症などがその例に挙げられます。
精神疾患により、同人がその結果を理解し、その上で、行動をすべきか否か判断することができなくなっている、といえる場合、その上で正常な判断をすることはできませんので、同人はやはり意思能力を欠く、ということになります。
何歳から肯定される?人の成長過程と意思能力
また、人は、生まれながらにして、自らの行為の結果を認識する精神能力を有しているわけではありません。
たとえば、0才や1歳の子は意思能力を有しません。これから、成長につれて、精神能力を身に着け、発達させていく前段階にあるといえます。
では、意思能力は何歳ころまでに身につくのでしょうか。
この点につき、絶対的な基準はありませんが、民法講義Ⅰ(近江幸治著 成文堂第5版)によれば、「人間は,だいたい,7~10歳になれば、この精神能力(意思能力)を有するものと一般に考えられている」とされています。
また、有斐閣の注釈民法総則(1)という書籍においては、「財産行為では7歳くらい」、「身分行為では―その人生に及ぼす影響の重大性に鑑み―15歳が、しばしば限界とされている。」と解説されています(初版246頁)。
意思能力の本質的な解釈
ところで、上記、有斐閣の注釈民法総則(1)は、財産行為が身分行為かで、必要とされる精神能力の程度が異なることが前提とされています。
他方、民法講義Ⅰ(近江幸治著 成文堂第5版)によれば、だいたい,7~10歳になれば、精神能力が備わる旨記載されており、すくなくとも当該頁においては、財産行為と身分行為とを分けた論述はされていません。
両者のよって立つ前提が異なるように感じませんか。
そう、ここでは、そもそも前提として、財産行為と身分行為とで、本当に必要とされる意思能力の程度は異なるのか、という点がクリアにされなければならないのに、その説明がないのです。
そして、実は、この問題は、意思能力の本質的な解釈にかかわります。
あ、今から述べる意思能力の意義に関する解釈論は、法律を本格的に学ぶ必要がある方向けです。
法律行為の類型ごとに分けて考えるべきか
財産行為と身分行為とで、要求される意思能力の程度を分けるべきか、という議論は、意思能力の解釈の本質的な問題につながります。
意思能力の有無は、法律行為ごとに(個々のケースごと)判断されるべきものなのか、人個人の一般的な属性から判断されるべきものなのか、という発想と重なるからです。
そして、この問題は、教科書等では、執筆者自らがよって立つ見解を前提にしながらも、特段の説明もされていないことが多いので、教科書を読むときの混乱のポイントになりがちです。
この点については、実は、身分行為と財産行為とで分ける、という考え方、法律行為ごとに判断すべきという考え方、いやいやそうではなくて、個々人の精神能力という一般的属性に応じて判断すべきだという考え方など、種々の見解がありえるところです。
そのため、意思能力がだいたい何歳くらいから認められる、などの記載を教科書で見つけた場合には、そもそも、その教科書の執筆者が、意思能力の意義につき、どのような見解に立っているのか、その前提を意識して読むのが理解の正確性を高める重要なポイントになります。
・意思能力の有無を個々の行為から離れて、人の属性から判断する見解
・人の属性のほか、法律行為の性質などを加味して意思能力の有無を判断する見解
後者の見解は、さらに財産行為と身分行為とに二分するなどの見解につながります。
民法改正第30会議事録
なお、上記の点については、民法改正の第30回会議議事録も参考になります。
同議事録によれば、松本委員が、意思能力を状況に応じて違うものと定義するのか,それとも一律のものとして定義するのかというところをまず議論するのが生産的である旨、述べた後、内田貴委員が次のように述べています。
「最も古典的には民法上の意思能力というのはかなり画一的なミニマムな能力を考えていたと思います。いわゆる心神喪失という言葉で表現されていたものですね。」
「ところが,その後だんだん学説が取引の類型に応じて要求される意思能力にも差があるのだということを言うようになり,その場合でもかなり低いところ,年齢としては7歳というような言い方がされたり,あるいは7歳から10歳と書かれている本もありますが,ある程度低いところで,しかし取引の類型によって差があるものを意思能力として考えていた時期がある。
さらに、内田貴委員は、上記に加え、意思能力につき、「もう少し高い経済合理的な判断能力があるかどうかというところで判断するものと3段階ぐらいある」という感じがする旨を述べています。
意思能力の意義をめぐる種々の見解がさらに細分化されている旨指摘されているわけです。
ただ、いずれにしても、内田貴委員の解説から、意思能力の意義そのものにつき、民法改正された現時点においても解釈上の争いがあることは明らかです。
そして、その後、同議事録では、意思能力の意義につき、種々の議論が交わされますが、結局、各種の考え方の内、民法がどのような考え方を採用するのかは、明文化されませんでした。
そのため、意思能力をどのように判断すべきか(個々人の属性を持って判断するのか、法律行為の性質などを加味するのか)は、形としては、建前論としては、依然として解釈にゆだねられている事項といえます
裁判における意思能力の判断
意思能力につき、法律行為ごとに判断すべきという考え方、個々人の精神能力という一般的属性に応じて判断すべきだという考え方など、種々の見解があることは上述の通りです。
では裁判ではどうでしょうか。
裁判実務では、法律行為の性質等を加味する立場が強いとされています。裁判例では、医学的な見地に基づく精神能力のみならず、法律行為の類型や性質、理解の困難さ、なども踏まえて判断される傾向です。
これは、大した事ない法律行為と重大な影響が及ぶ法律行為とでは、求められる意思能力の程度も異なるのだ、という発想です。
この点については、後述の平成30年8月9日の東京地裁判決も参照にしていただけると幸いです。
権利能力・事理弁識能力、行為能力との違い
さて、次に、権利能力、事理弁識能力、行為能力と意思能力との違いについて見ておきましょう。意思能力の理解が深まるはずです。
権利能力との違い
権利能力は、人が人であるがゆえに持つ能力で、権利義務の主体となりうる地位のことを指します。精神能力とはそもそも無関係で、人であれば当然に有している能力です。
権利能力というのは、社会生活のステージにたつ能力です。リンク先で権利能力について解説していますので、ぜひ民法3条1項のカッコよさ、感じてください。
行為能力との違い
行為能力というは、単独で有効な法律行為を行いうる能力のことを指します。被後見人、被保佐人、被補助人は、行為能力を一部制限されています。未成年者も行為能力を欠く者です。
行為能力の制限は、法律又は裁判所の判断によるものです。精神能力そのものではなく、精神能力が不足していることを理由に、法律又は裁判所の判断によって、法律上の行為を単独で有効にできなくなるものです。
単独でなされたその行為は原則として取り消しの対象となります。
なお、意思能力の概念との対比においては、行為能力は、自然発生的な個々人の能力・状態ではなく、法律における制度上の能力であるという点が理解のポイントです。
行為能力の概念は、制限行為能力制度という制度の下でのみ機能します。民法改正前から概念されていた意思能力とはまるで別物です。
第1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
第2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第3項
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
参照:民法第6条
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
事理弁識能力
事理弁識能力(事理を弁識する能力)は、被後見人や被保佐人、被補助人の選任要件を規定した民法7条等に規定される精神能力です。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
この事理弁識能力は、行為能力制限にかかる審判の前提となる精神能力です。法律行為の意味を理解して、判断できる精神能力を指します。
精神能力を指す点で意思能力と共通です。行為能力より、よほどこの事理弁識能力と意思能力との違いのほうが理解は難しいはずです。
さて、この事理弁識能力ですが、上記に述べたような意思能力の意義の解釈によっても影響を受けるのですが、意思能力がない場合は、日常的な取引行為も無効と判断されますので、大雑把に言えば、事理弁識能力は、意思能力よりも精神能力がある場合を前提しているものと理解されます。
また、事理弁識能力は、被後見人等を選任するための要件であり、ある時点における特定の法律行為と結びつけて判断されるものではありません。事理弁識能力は、特定の法律行為を想定せずに,人に着目して判断される能力である、と理解されます。
後見などの審判の際、個別の法律行為は審理対象とならず、人の属性を見る、というわけです。そこでは、裁判において意思能力の判断に際して加味されうる「特定の法律行為の性質・困難性」などは審理の埒外です。
意思能力に関する判例・裁判例
さて、最後に、意思能力に関する判例を見ていきましょう。
明治38年5月11日大審院判決(意思無能力者の行為は無効)
もっとも有名なのはこの判決ですね。
「事実上意思能力を有せざりしときは、その行為は無効たるべく・・・全く意思能力を有せざる事実あるにおいては、何ら取消の意思を表示することなく当然無効たるべきは誠に明白なる法理なり」
なお、この判決は、法律の明文で、意思能力を欠く者の行為は無効である旨定められる前の判決です。
意思能力を欠く者の法律行為は、それを規定する法律の有無を問わず、無効とされてきたわけです。
平成30年8月9日の東京地裁判決
もう一つ、有名なものではありませんが、認定の勉強用に裁判例を見ておきましょう。
事案の概要・着目点
この平成30年8月9日の東京地裁の裁判例は、左中大脳動脈梗塞を発症し、ウェルニッケ失語症という後遺障害を負った者が連帯保証契約を行った際の意思能力の有無が争われた事案です。
ここで見てもらいたいのは、医学的な見地のみならず、法律行為の性質・困難さも意思能力欠如認定の考慮材料となっている点です。
考慮要素
この判決は、医療機関の診療録や鑑定結果を丁寧に認定したうえで、さらに次のような事情を加味して、意思能力の欠如を認定しました。
・本件契約書は、契約条項を含め4枚に及ぶものであって必ずしも単純なものとはいえない上、本件連帯保証契約は、本件会社の控訴人に対する元本3億1310万円の借入債務を連帯保証することを内容とするものであって被控訴人に多大な影響を与えるものであること
・被控訴人がウェルニッケ失語症の発症前において、本件会社の多額の債務を保証するなどしていたことはうかがわれないこと
同判決は医療記録や鑑定結果に加え、上記のような事情を挙げたうえで、「以上の諸事情を総合考慮すると、被控訴人は、本件連帯保証契約を締結した平成26年8月25日当時、本件連帯保証契約及びその前提となる本件貸金契約の法的な意味を理解する能力を欠いており、意思能力はなかったものと認められる。」と結論付けたものです。
ここで、認定のポイントは、契約書が単純なものではないこと、法律行為が本人に多大な影響を及ぼすこと、これまで、被控訴人が多額の債務を保証するなどしていた経験がないことなどを考慮要素に挙げている点です。
契約書が単純なものでないことなどをも考慮要素に挙げていることからすれば、法律行為の困難性を意思能力の有無の判断要素としているように見るのが自然ではないでしょうか
判断基準・確認方法
以上のような判決内容などを前提とすれば、精神疾患を理由とする意思能力の有無は、医師の診断・症状のほか、法律行為がなされた時点における周辺事実、法律行為の内容などに照らして、意思能力の有無を判断することになりそうです。
意思能力につき、個々人の精神能力(属性)を医学的な見地からのみ判断するのではなく、法律行為の類型やその方式の理解の困難性等を考慮要素としています。
そうすると、個別具体的な事案においては、意思能力の有無は、医師の診断のほか、具体的な症状の内容、日常行為などを自律的に行い得たか、否かなどを確認、チェックが重要といえます。
意思能力に不安があるときには、あまり難しい契約などを求めるのはリスキーといえそうです。