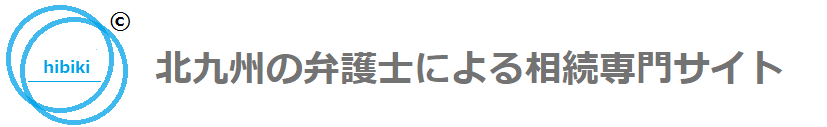民法には、心裡留保という言葉が有ります。これは「しんりりゅうほ」と読みます。
日常用語としてまず出てこないので、イメージしにくいのですが、意思表示に関する重要な用語の一つなので、押さえておきましょう。
心裡留保とは
法律的な用語でいえば、内心的効果意思を欠くことを知りながら意思表示をしてしまう場合です。
※ 法律的な意思表示の構造については次のページをご参照ください。
法律から離れて考えてみる。
まずは、法律から離れて考えてみましょう。
中学生のA君がBさんのことを好きになってしまったとします。しかし、Bさんに「私のこと好きなの?」と聞かれたA君は素直に「好き」といえません、自分の気持ちは分かっていながら、「そんなんじゃない」と答えてしまいます。
どうですか、A君、内心と自らの言葉とが一致しないことを知りながら、真意と違う「そんなんじゃない」と、言ってしまっていますね。
これが、心裡留保です。たとえの例がおっさんじみてますかね(笑)
法律にいう心裡留保の具体例
法律にいう心裡留保もこれと似たようなものです。心にもないのに、言ってしまう、そういったことが世の中にはあるのです。
たとえば、本当に贈与するつもりもないのに、それを分かりながら「この車お前にやるよ」というのは、贈与にかかる心裡留保です。
その他、たとえば、雇うつもりもないのに「雇ってやる」、などというのは、雇用契約にかかる心裡留保です。
真意と異なることを知りながら、契約を行う等する行為を心裡留保といいます。
なお、裁判で具体的に心裡留保が問題となった事案については、次のページで紹介しています。心裡留保についての理解は深まると思いますので、ぜひご参照いただけますと幸いです。
冗談に似ている
上記の例からも伺えますが、心裡留保というのは、「冗談」に似ています。
たとえば、現に贈与する意思もないのに、相手をからかうつもりで(冗談で)、「贈与するよ」などと言ってしまうケースです。
心裡留保の効力 冗談は本当になる!?
では、ある契約が心裡留保でなされたものと評価された場合、その契約の効力はどうなるのでしょうか。
民法は、この点に関し、原則として「有効」と扱っています。
内心と表示が違うと知りながら、意思表示を行った場合、意思表示は原則として有効です。有効ということの意味は、契約が有効に成立する、という意味になります。
ただ、民法の規定上、例外が設けられています。それは、その相手が、内心と表示が違うと知っていた、又は知り得た場合です。
たとえば、実際に売るつもりもないのに、売主の「売る」という申込に対して、買主が商品を買う、と言った場合、この契約は原則として有効です。
ただ、買主が、「売主は実際に売るつもりはないだろうな」と売主の内心を知り、又は知り得た場合には、当該契約は例外的に無効となります。
この場合、契約を有効に成立させて、買主を保護する必要が無いからです。
心裡留保の要件と要件事実
少し、プロパーな話となりますが、ここで要件事実について。
①内心(効果意思)と表示内容との不一致
②表意者が、①を知っていたこと。
③相手方が表意者の真意(内心)を知り、又は知ることができたこと
なお、要件事実というのは、裁判となった時に誰が何を証明しなければならないか、という点に関する議論です。
難しければ読み飛ばしてくださいね。
心裡留保に関する民法の規定
要件事実の話をするので、先に民法改正前の93条と改正後の民法93条1項を挙げておきます。
改正前民法93条
改正民法93条1項
3つの要件事実
改正後の心裡留保の条文上の要件(条件)をおおざっぱに整理すると次の①、②、③となります。
①内心(効果意思)と表示内容との不一致
②表意者が、①を知っていたこと。
③相手方が表意者の真意(内心)を知り、又は知ることができたこと
これは、改正前に書かれたものですが、「要件事実マニュアル」(ぎょうせい 岡口基一著)という書籍を参考にした整理です。
なお、条文の体裁上、上記①と②が民法93条本文に書かれており、③が但書に書かれているため、要件事実の理解としては混乱しがちですが、①~③全て表意者側が主張・立証していくことになります。
要件事実①~③につき若干の補足
要件事実①~③につき若干内容を補足します。
①内心(効果意思)と表示内容との不一致
思っていたことと実際に喋ったことが違うよ、という意味ですね。たとえば、実際にあげる意思もないのに「贈与する」と述べたことを指します。
②表意者が、①を知っていたこと
表意者が内心と表示内容とが違うことを分かってしゃべっていた、という意味です。実際にあげる意思もないことを表意者が分かっていた、ということを指します。
③相手方が表意者の真意(内心)を知り、又は知ることができたこと
相手が、表意者の内心を知っていたか、又は知ることができた、という意味です。
なお、改正前民法では、条文上、「知り又は知り得た」の対象となる事実は、「意思表示が表意者の真意ではないこと」とされていましたが、改正後は、「表意者の真意」が対象となっています。
第三者の保護について
次に第三者の保護についてです。
たとえば先ほどの売買契約の例で、心裡留保で売るといった売主から商品を買った買主がこれを第三者に転売した場合に、転売で買った者が保護されるか、という点
結論を言えば、善意であれば保護されます。
民法94条2項の類推適用(従来の学説)
この点に関し、従来の学説は、民法94条2項という規定を類推適用して保護を図る、としてきました。
おおざっぱに言えば、転得者は、心裡留保につき善意(知らなかった)場合に保護される、としてきました。
民法93条2項が新設
今般の民法改正では、上記の点が手当てされています。具体的には、民法93条に第2項が置かれました。
その内容は次のとおりであり、善意の転得者が明文の規定により保護されることになりました。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
代表権・代理権の濫用と最高裁の判例
最後に、改正前の民法93条が輝いた場面に、会社の代表者が代表権を濫用した等の事案に関する最高裁の判例法理(昭和38年9月5日最高裁判決等)がありますので付言しておきます。
会社の代表者が代表権を濫用して取引をする場合、会社代表者は、会社としての意思決定と自らの代理行為との齟齬を知りながら、取引を行っています。
この会社社内の意思とこれと異なる代表者の法律行為との関係は、あたかも自然人における内心と表示内容との不一致と類似します。
そこで、こうした代表権・代理権の濫用の場面に関し、最高裁は、民法93条但書を類推適用して事案の解決を図ることとしてきました。
本来的な場面ではないものの、この代表権・代理権濫用事例は、改正前の民法93条がクローズアップされる重要な場面の一つです。