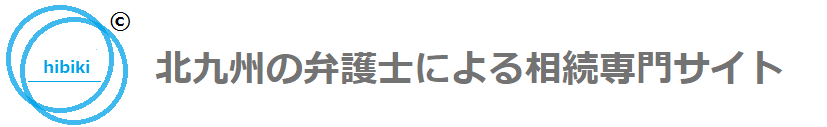今回のテーマは、時効取得についてです。
時効取得は民法において権利発生原因の一つとして重要なテーマとなりますし、実社会においても、重要な機能を担っています。
そこで、以下、時効取得について、説明していきます。
取得時効とは
取得時効とは、所有権その他の財産権を、長期にわたり自己の所有物または自己の権利として(準)占有していた場合に成立する仕組みのことを指します。
大雑把に言えば、自分の権利だと思って、一定期間、それを(準)占有をしていた場合に、実際にその権利が自分のものになる、という制度です。
民法においては、162条から165条に規定されています。
なお、取得時効の制度や仕組みを指す場合には、「取得時効」といい、これによる物権変動を指す場合には、「時効取得」という言葉が使用されます。
あまり意識されることはないかもしれませんが、「取得」という用語と「時効」という用語が入れ替わっている点にご注意ください。
時効取得の例
取得時効の例を一つ上げてみましょう。
たとえば、私が20年間、自分のものだと思っていた使っていたある土地が、実際には他人の土地だったとします。
本来であれば、その土地は他人の物ですから、その他人から請求された場合、私は当該土地を返還しなければなりません。
また、その使用利益も返還の対象となります。
しかし、私が自分のものだと思って占有(支配)を続けたことにより、同土地を時効取得した場合、その土地は私の所有物になります。そのため、元々の土地の所有者から請求を受けても、私はその土地を返還する必要がない、ということになります。
しかも、時効取得の効果は、私が占有(支配)を開始した時点にさかのぼって発生しますので、使用利益の返還も不要となります。
要件
では、時効取得はどのような場合に生じるのでしょうか。以下、議論の中心となる所有権の取得時効の成立要件を見ていきます。
所有権の取得時効について定めた民法の規定は162条です。
第1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
第2項 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第1項は、20年の長期取得時効について定めた規定です。また、同2項は10年の長期取得時効について定めた規定です。
同2項は、「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかった」ことを成立要件とする一方で、第1項の場合よりも10年間分、必要な占有期間を短く設定しています。

なお、厳密に言えば、取得時効の効果を確定的に発生させるには、さらに時効援用が必要です。また、10年ないし20年という期間については、更新ないし完成猶予という仕組みの下、完成しないこともります。これらについては別の機会に解説しています。
所有の意思(自主占有)
上記各要件の内、所有の意思というのは、当該物について、所有者と同様の支配を行おうとする意思を言います(また、その意思に基づく占有のことを自主占有)といいます。
大雑把に言えば、対象となる土地や動産につき、所有者のようにふるまう意思のことを指します。
たとえば、ある土地につき、ずっと賃借人として賃料を支払い続けていた場合はどうでしょうか。
この場合、土地を占有していても、それは他人の土地を借りて占有しているにすぎず、自ら所有者としてふるまっているわけではありません。
そのため、この場合には、所有の意思は否定されます。
なお、ある物を占有している場合、民法186条1項(後述)により、所有の意思は推定されます。
そのため、取得時効を主張しようとする場合、自ら自主占有であることを証明するまでの必要はありません。他主占有であるとの相手方の主張が裏付けられない限り、自主占有は否定されません。
なお、自主占有か否かは占有開始の原因や占有に関する事情から、外形的に判断されます。したがって、自主占有であることを否定したい相手方は、他主占有をうかがわせる外形的事情を主張・立証していくことで上記推定を覆していく必要があります。
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する
平穏・公然
また、上記民法162条では、時効取得の要件につき、平穏性・公然性が要求されています。
暴力を用いて占有をしているような場合には平穏性は否定され、また、あえて秘密裏に占有を隠している、といった場合には公然性が否定されます。
占有
時効取得の要件となる「占有」は、当該物を自らのために所持・支配していることをいいます。
ある動産を事実上所持している場合はもちろん、他人のある土地に家屋を建ててているといった場合にも、その家屋の建築を通じた土地の占有が認められます。
また、他人を通じて、占有をしている場合(間接占有)をしている場合にも、時効取得は成立しえます。
Aさんが、Bさんの建物を自分の不動産だと思ってCさんに賃貸しているといった場合でも、当該建物を間接的にAさんが占有しているといえ、時効取得が成立しえます。
占有ってなんだという方はこちらをご参照ください。占有概念について解説した記事です。
10年前から現在まで占有していたという場合に、その中間地点においても占有していたことを、時効取得者は立証する必要があるでしょうか?
この点については法律の手当があり(民法186条3項)、時効取得を主張したい側が、占有の開始と終わりを主張・立証した場合、その間の期間も占有していたとの推定が働きます。
したがって、その間の期間の占有の事実を覆す事情が相手から主張・立証されない限り、占有は継続していたものと扱われます。
善意・無過失
以上の「所有の意思」「平穏・公然」を満たして20年間「占有」が継続した場合、長期取得時効が成立します。
これに加えて、時効援用があれば占有者は当該物を時効取得します。
他方、短期消滅時効の成立には、これに加えて、「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかった」ことが必要となります(民法162条2項)。
善意について
ここで、善意といえるためには、諸説あるも、自分に所有権があると信じていたことが必要です。
人のものではない、と信じていただけでは足りず、自分のものであると信じていたことが必要です。
なお、この善意についても、上記民法186条1項で推定されます。
無過失について
短期消滅時効の主観的要件として、主として問題となるのは「無過失」の要件です。この無過失については推定規定がないため、時効取得者側で証明する必要があります(判例及び多数説)。
そして、大審院大正2年6月16日判決によれば、ここでいう過失とは「相当の注意を払えば、権限の瑕疵を発見できたにも関わらず、注意が不足したためにその発見ができなかったこと」(管理人において現代語化)を意味するものと解されます。
それゆえ、大雑把に言えば、「自分には本権が無いとの事情を分かりえたのに、必要とされる注意を欠いた結果、その事情を発見できなかった」と言えるか否かが、無過失か否かの分水嶺となります。
たとえば、不動産の売買に際しては登記をチェックするのが通常ですから、土地などの不動産の売買を契機に占有が開始されたが、実は無権利者からの売買であったというような場合に時効取得者たる占有者が登記をチェックしたか否かは一つの重要な要素となります。
また、この点については、大審院大正15年12月25日判決が「登記上の所有者と表示された者を所有者と信ずるのは、特別な事情がない限り、過失ありということはできない」(管理人において現代語化)旨判示しているのが参考になるところです。
占有の開始の時点において
また、民法162条2項においては、上記の善意・無過失の要件は、「占有の開始の時点において」必要とされています。
占有の開始の時点の占有者の主観を見て、善意・無過失だったといえるか否かを判断するわけです。
しかし、条文上、「占有開始の時点において」とされていることを反対に読めば、占有開始の後の主観は問われないことになります。
そのため、たとえば後から悪意になったとしても、10年間自主占有を継続すれば、短期時効取得は成立しえます。
ここまでのまとめ
以上、時効取得の一般的な要件を見てきました。次の要件を満たせば、後は時効援用の意思表示によって、取得時効の効果(所有権の取得)が発生することになります。
<再掲>

なお、不動産を時効取得した場合、そこに税金が課せられることがあります(一時所得)。財産は取得できるけど、それに対して、一時所得として課税されうるということは、時効援用をすべきか否かの考慮要素の一つとなり得ます。
土地の時効取得と登記について
さて、ここからは応用です。
上記のような要件のもと土地を時効取得した場合、実際上は、次に、土地の名義移転の問題が生じます。
時効により土地を取得した場合でも取得、それを第三者に公示するには、登記上の名義を移転する必要があるからです。
では、時効取得者は、登記変更をどのように行えばいいのでしょうか。
時効取得と共同申請の原則
不動産登記法においては、登記移転につき、登記義務者と登記権利者とが共同申請しなければならないとの原則がとられています。
時効取得により土地を取得した場合も同様で、名義を移転するためには、原則論としては、時効取得した者とされた者とが共同で登記を申請することが必要になります。
つまりは相手方の協力を得て、登記を移転すればよいということです。
裁判になることが多い
・・・でも、ちょっと待ってください。
通常の売買などにおいてはともかくも、時効取得をめぐる場面で、時効取得された側が、「はい そうですか」と共同申請に応じてくれることはなかなか想定しにくいのではないでしょうか。
法的な問題のほか、そこには、「時効取得!?認めないぞ」という感情的な問題も生じえます。
このように時効取得された側の協力を得ることができない場合、登記の移転を求めるには、時効取得者から、登記を移転せよという裁判を起こすことになります。
裁判における確定判決があれば、これを債務名義として権利者側が単独で登記申請を行うことが可能です。
そのため、時効取得者側から登記を移転せよという裁判を起こす、というわけですね。
なお、実際上、ここで注意を要するのは、不動産の時効取得に関する対抗要件の問題です。
実は、時効取得者は、時効完成後に現れた第三者との関係では対抗関係に立つという判例法理があります。
この判例法理に照らすと、裁判等を起こして登記を移転せよと請求した場合でも、土地を取得された者が事後的に第三者に土地を処分して登記を済ませることで、時効取得者による登記移転請求が成り立たなくなる可能性があります。
なお、これを防止するために、請求側で、土地の処分禁止の仮処分などを行っておくことも考えられますが、実はこの手段も土地の一部の時効取得などが問題となるケースでは現実性を欠く場合があります。
この点については、神戸学院法学第41巻第3・4号に詳しいので、ご関心のある方は確認されてみてください。かなり難しい問題が存在します。
時効取得と相続
さらに、応用として時効取得と相続の問題に続きます。
時効取得をめぐっては、相続人の一人が相続後、占有している財産などにつき、ほかの相続人との関係で時効取得が成立するか、という論点があります。この点を考えてみましょう。
原則的には所有の意思が否定される
まず、原則はどうなるか。
上記取得時効の要件に沿って考えてみれば、相続人の一人が、相続開始後、ある財産を一人で占有しているからと言って、時効取得は成立しないこととなります。
なぜなら、相続人が複数ある場合、遺産は相続人みんなの財産であると考えるのが普通であり、自分一人の財産である、と考える自己所有の意思に欠けると考えられるからです。
みんなの遺産だと考えている相続人の一人が占有を継続したとしても、それはみんなの遺産として占有しているにすぎず、自己所有の意思は認められません。
相続人の一人による時効取得が成立する場合
しかし、判例においては、例外的に、相続人の一人が、ほかの相続人との関係で、相続財産を時効取得しうる場合があるとされています。具体的には、昭和47年9月8日の最高裁判決(後述)がそれです。
同判決は、次のような要件のもと、相続人の一人による遺産の自主占有を認めています。
・共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わなかったこと
・相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきたこと
・これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかったこと
かなり厳格な要件(ないし要素)ですが、相続財産につき、相続人の一人が、遺産を時効取得しうることを認めた重要な判決の一つと言えます。
相続人一人による時効取得を認めた判例
参考までに上記最高裁の判旨をそのまま掲載しておきます。なお、同判決は、具体的なあてはめとしても、時効取得をみとめたケースです。
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかったような場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当である
ちなみに、同最高裁判決の控訴審も、時効取得を認めうる旨判断しています。理由付けが参考となりますので、併せて紹介しておきます(管理人において現代語化したもの)。
「相続は占有の態様を変更すべき新権原ということができないにせよ、本権の承継を伴う意味において新権原に近く、しかも、相続が単独相続であるか共同相続であるか明らかでない場合も稀ではなく(被相続人に婚姻外の子があるような場合に考えられよう)、共同相続人の一人が単独相続をしたものと誤信することもありうる」。
そのため、「共同相続人の一人が単独相続をしたものとして相続財産を現実に占有し、その管理、使用を独断専行してその収益を独占し、自己のみの名において公租公課を納付しているような場合には、その相続人は相続財産を単独相続したものとしてこれを自主占有するものとするに妨げないと解すべきである。」
時効取得と相続をめぐっては上記のような問題のほか、時効取得の成否をめぐって占有が相続によって承継されるか、他主占有が自主占有に代わるかなどの論点があります。
この点については、上記関連記事にて解説予定としています。併せてご参照いただけますと幸いです。