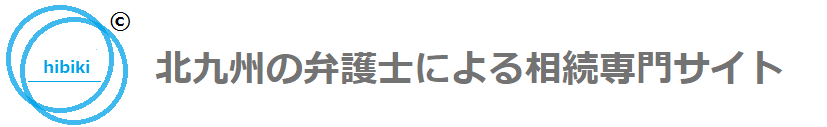錯誤の要件の一つとして、「当該錯誤が重要であること」という要件があります(民法95条)。
改正前民法においては、民法95条の錯誤の要件として、「要素に錯誤があること」が求められていましたが、改正民法の下では、これに代わり、「錯誤の重要性」が要件となりました。
ただ、この重要性の要件の解釈については、改正前民法下における「要素」に関する判例・裁判例の解釈が踏襲されるものと予想されます。
また、従前、学説上、錯誤に含むか否か争われていた動機の錯誤について、今般、改正民法で手当てされました。
ただ、その解釈に際しても、やはり改正前民法における判例が参考になります。
そこで以下、要素に関する判例及び動機の錯誤に関する判例を俯瞰します。併せて、重大な過失が認められた事例について、裁判例を紹介します。
改正民法における条文上の要件、効果については次の記事でまとめています。錯誤って?という方はぜひこちらをご確認ください。
「要素」についての判例の解釈
以下、要素の錯誤に関する判例を見ていきます。
要素に錯誤が有る場合とはどういう場合か
この点に関し、まず大審院は次のように述べています(ひらがなに直しています。)。
法律行為の要素とは、法律行為の主要部分を指称する。
これだけでは、判断基準としては不明確ですが、大審院は次のようにも述べています(注 カタカナで表記された部分を当ブログにおいて現代語風に変えています。)
「表意者が事情を知っていた場合には、其の意思表示を為さなかったと忖度される場合」をいう。
要は、表意者に錯誤が無ければ、その意思表示をしなかったであろうと考えられる場合が要素の錯誤、というわけです。
判断の基準
では、その意思表示をしなかったと言えるか否かは、本人基準で判断するのでしょうか、それとも客観的に判断されるのでしょうか。
この点について、大判は、次のように述べています(当ブログで現代語約にしています。)。
①法律の要素か否かは、まずもって表意者の意思を標準とすべきであることは明白である。②ただし、通常人を表意者の立場に置いてもまた同一と認められることを要する。
この判例の立場については種々の評価があるものの、本人基準はもちろん、通常人基準をもクリアした場合に錯誤が主張できる、という立場と解されています。
要は、要素に錯誤が有ると言えるためには、①本人自身がその錯誤がなければ当該意思表示をしなかったであろうと言え、かつ、②通常人を基準としても、同様といえることが必要となります。
もっと端的に言えば、①本人自身がその意思表示をしなかったであろうと言えることが、②また普通に考えても、それが確かにもっともだ、といえることが要求されます。
なお、改正民法95条においても、重要性の有無は、「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして」判断するとされており、これまでの判例の判断基準・判断基底が踏襲されているものといえそうです。
動機の錯誤について
動機の錯誤については、大審院の時代から最高裁までいくつか判例があります。
実際の生活で生じ得る錯誤に関するトラブルのほとんどのケースは、動機等その縁由に関して認識と事実に食い違いがある場合であるとも指摘されており、実際、判例・裁判例は、動機の錯誤に関する事例を中心に積みあがっています。
動機の錯誤に関する有名判例を見ていきましょう。
大審院判例
大審院は、馬を良馬と信じて取引が行われたケースにおいて、次のように述べています(現代語訳にしています。)。
法律行為の要素に錯誤があって、その意思表示の無効たるは、意思表示の内容を為す主要部分に錯誤あるがために他ならない。しかして、物の性状の如きは通常、法律行為の縁由たるにすぎず、その性状に錯誤あるがために法律行為の無効をきたさないことは論を待たない。
ただ、表意者がこれをもって意思表示の内容を構成せしめ、その性状を具有しない場合において、法律行為の効力を発生させることを欲せず、しかも取引の観念事物の状況に鑑み、意思表示の主要部分となす程度のものと認められるときは、その錯誤は意思表示の無効をきたすものというべきである。
縁由部分が意思表示の内容を構成し、かつ、そこに食い違いがある場合において、当該縁由部分が意思表示の主要部分と言える場合に、錯誤が成立するとの立場です。
最高裁の判例
同趣旨の判断は、最高裁でもなされています。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り法律行為の要素とならないものと解するを相当とする。
改正民法95条
ここで、改正民法95条を見てみましょう。
改正民法95条は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」が有る場合、「意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」と定めています(同1項2号、同2項)
この条文は、動機や性状の錯誤を主張できる条件に付き、法律行為の基礎とした事情が相手に示されていることが必要とするものです。
実質的には、上記大審院や最高裁の立場を条文化したものと評価できます。
重大な過失について
重過失有る場合、錯誤を主張できない。
ただ、判例上、比較的緩やかに重過失は認定されうる。
改正前民法においても、改正後の民法においても表意者に重大な過失がある場合、表意者は原則として錯誤を主張できません。
改正民法95条3項
まず、民法改正後の95条3項を確認しましょう。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
この条文にいう重大な過失についてですが、どの程度の注意義務違反に達している場合に重過失と言えるのかについては、よくよく注意をしておく必要があります。
法律上、重過失が要件とされる場合、その程度として、悪意にほぼ近い状態、悪意と同視しうるレベルの注意義務違反まで求められることがあります。その結果、その立証が不可能ないし著しく困難といえるような場合もあります。
ただ、民法95条3項柱書の表意者の重過失については、比較的緩やかに認定がされているように思われます。注釈民法という本でも、この点に関し、取引の安全の見地から、重過失は緩やかに認めてよいであろう、とされていました。。
もちろん、重過失という以上、軽過失ではだめですが、この要件は、およそ立証困難なめちゃくちゃ厳しい要件というわけではないことにつき、民法95条を理解する、という意味で、意識の片隅にでもおいといてください。
裁判例について
重過失が肯定された事例はいくつもありますが、以下、3つほど裁判例を紹介します。
土地の売買に関し、代金支払の意思、能力に関する錯誤が要素の錯誤に該当するとした上で、売主が買主の資産状態、代金支払能力等につき調査をしなかった他、売主があえて所有権移転登記をさきに済ませることなどの危険な売買条件を承諾した点などを考慮要素に挙げて、売主に重大な過失があるとされた事例。
行政上の許可を要する営業店舗の敷地として、当該敷地を購入したという取引につき、買主が、適法に当該営業の許可を得られると誤信していたケースで、買主が現地を十分に調査しなかった等の点につき、重過失があると判断された事例
物上保証人が他にいると誤信して連帯保証人となったというケースで、要素の錯誤は認めつつ、物上保証人の登記申請委任状の印影の偽造が肉眼でも容易に知り得たこと等を根拠に連帯保証人に重過失があるとされた事例。