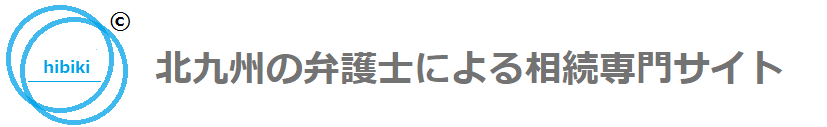今回は、民法上の錯誤の意味合いについて、詳細に見ていきます。
改正法における民法95条規定の要件や条文の構造を追うだけでも大変だと思いますが、重要な規範ですので、一度確認しておきましょう。
民法上の意味における錯誤とは
たとえば、100万円で買う、と言おうと思っていたところ、つい200万円で買う、と言ってしまった等の例が教科書では挙げられます。
また、後述の通り、改正民法では、「錯誤」の概念に動機の錯誤なども含まれるようになりました。
これは、意思表示をしようと思った理由に誤解があった場合を指します。
ここで関連記事を紹介!
錯誤という言葉は日常用語としても使用されます。
また、法律学においては、刑法でも登場します。
その用語法や意味については、次の記事で解説していますので、一度ご確認いただければ幸いです。
もう一つ関連記事を紹介!
民法における錯誤は、表意者が内心と表示との食い違いを知らない場合です。
真意と異なると知りながら、「わざと」なされた意思表示は「心裡留保」といいます。
錯誤の二つの類型(民法95条第1項)
改正民法によれば、錯誤は、次の二つの種類に分かれます。
第1類型⇒意思表示に対応する意思を欠く錯誤
第2類型⇒表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
改正民法95条第1項を見てみましょう。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
ここでまず着目してほしいのは、①と②です。
改正民法において、「錯誤」はこの二つに分類できることになります。
改正民法後の定義を述べろと言われたら、形式的には、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤及び、②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と答えることになります。
第1類型「意思表示に対応する意思を欠く」場合
第1類型の錯誤は、従来、①表示、②内容の錯誤と呼ばれていたものです。
表示の錯誤とは、表意者が、表示[表現]を誤ってしまった場合です。
内容の錯誤とは、表意者が表示の「意味内容」を誤ってしまった場合です。
表示の錯誤
表示の錯誤というのは、たとえば、「100万円で買う」と言おうと思っていたところ、うっかり「200万円で買う」、と言ってしまった場合の例がこれに該当します。
また、契約書に1000円と記載しようと思っていたところ、誤って1000万円と書いてしまった場合もこれに該当します。
内容の錯誤
内容の錯誤というのは、要は表現・用語の意味内容を誤解していた場合です。
たとえば、ドルとカナダドルが同じ価値を有するものだと思って、20カナダドルの商品につき、20ドル支払うなどと言ってしまった場合がこれに該当します。
第2類型「表意者が基礎とした事情」について誤解がある場合
錯誤のもう一つの類型は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(改正民法95条第2号)です。
動機などの意思形成過程に誤解が有る場合を想定するものです。
以下、基礎事情の錯誤ということもあります。
条文の意味
この文言、すごく「分かりにくい!」のですが、要は、内心の形成過程に問題がある場合を規律する規定です。
そこには動機などに錯誤が有る場合や、意思形成の理由となった目的物(商品)の性質に関する誤解があった場合なども含まれ得ます。
実生活で重要なのは、第1類型よりもむしろこちらの第2類型のほうです。
具体例
第2類型の錯誤の典型例の一つは動機の錯誤です。
たとえば、ある商品がとても優れた商品であると理解して、その商品を買う、と述べたところ、実際には、当該品質・性状を備えていなかった場合などが挙げられます。
不動産売買契約や賃貸借契約等において、この動機の錯誤の主張は、しばしば登場します。
議論の解消
改正前民法化においては、動機に齟齬がある場合にこれが民法上の錯誤に当たるか否か議論がありました。
しかし、改正民法施行後においては、上記の通り基礎事情にかかる認識と事実の不一致が錯誤に含まれるようになりました。
動機の錯誤も民法95条2号が定める第②類型に含まれことが明確化されたといえます。
民法95条が定める要件
以下、民法95条が定める要件(錯誤を主張するための条件)について見ていきます。
基本的要件
錯誤を主張するための基本的な要件は、次の①~③ないし③です。③は、第2類型の錯誤の場合のみ必要となります。
①意思表示が、錯誤に基づいてなされたこと
②当該錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
③法律行為の基礎とした事情につき、法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと
各要件について
それぞれの要件について簡単に見ていきます。
①の要件について
①錯誤を理由にある意思表示を取り消すには、当然ですが、対象となる意思表示が存在することが必要になります。
そして、当該意思表示が「錯誤に基づく」と言えることが必要です。
要は、「意思表示」と「錯誤」との間に「因果関係」があると言えることが必要になります。
②の要件について
また、軽微な錯誤がある場合に、その取り消しを認めると取引の安全が害されます。
そこで、②民法は、当該錯誤が重要なものと言える場合に限り、取消を認めることとしました。
なお、この要件は、錯誤無効が認められるためにはその「要素」に錯誤がなければならない、という改正前民法における要件に相応するものです。
③の要件について
③の要件は、第2類型つまり基礎事情の錯誤の主張にのみ必要とされる要件です。
民法95条2項により、動機などの基礎事情が意思表示の一部として相手に表示されていることが必要となります。
これは、従前の判例の解釈を踏襲した立法です。
ここで関連記事の紹介!
以上に述べた要件論の理解をより深くするには、民法改正前の判例・裁判例の解釈が非常に有用です。
また、後述の「重過失」の程度は結局どのレベルで求められるか、などの点は、裁判例を追いかけなければ分かりません。
この点については、次のページに記載していますので、ご参照願えれば幸いです。
条文の確認
ここで、基本的要件を定める条文を確認します。95条1項(再掲)と同2項です。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
②意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
「重大な過失」⇒例外的に錯誤主張を封じる
民法95条1項、2項が定める基本的な要件は上記①~③ないし④のとおりです。
その要件を満たす場合、原則として表意者による錯誤取消の主張が認められます。
ただ、例外的に、表意者が錯誤主張をすることができなくなる場合があります。
表意者に重大な過失がある場合です。
「重大な過失」とは、ちょっと注意を払えば気づけたにも関わらず、不注意によって、錯誤に陥っていた場合をいいます。
大ざっぱに言えば、「それ、ふつうは気付けるよね」という点に錯誤がある場合です。
この場合、表意者が錯誤に陥っていても、表意者は取消の主張ができません。
たとえば、「Aを買う」との内心において、「Bを買う」、との意思表示をしてしまった場合を例にとると、Bを買うとの意思表示をしてしまった表意者に重過失があるとされるときは、当該表意者は取消権を行使できなくなります。
相手方悪意・共通錯誤⇒例外の例外で錯誤主張可
もっとも、表意者に重大な過失がある場合でも、次の二つの場合には、例外の例外として、表意者は錯誤を主張し得ます。
・相手方が悪意である
・共通錯誤がある
相手方悪意の場合と共通錯誤の場合
民法95条3項によれば、錯誤の基本的要件を満たしても、重過失ある表意者は、例外的にこれを主張することができなくなります。
ただ、相手方が、表意者が錯誤に陥っていることを知っていた場合と双方とも錯誤に陥っていた場合は、例外の例外として、重過失ある表意者も錯誤取消を主張することができます。
そもそも、相手方が悪意の場合、表意者の錯誤主張を否定してまで、相手方を保護する必要はありませんし、共通錯誤の場合、相手も錯誤に陥っており、現になされた「表示」を重要視する必要がないからです(成立した契約などが、相手の真意にも反している状況です。)。
そこで、民法は、このような場合には、重過失ある表意者にも錯誤主張が可能と規律しました。
民法95条3項
以上の点につき、煩雑ですが、民法95条3項を確認しておきます、
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
民法95条が定める効果(取消)について
続いて、錯誤の効果について解説します。
「無効」から「取消」へ
改正前の民法においては、錯誤の効果は「無効」とされていました。
これが改正により、取消へと変わっています。
その結果、主張適格や意思表示、消滅時効などの点につき、取消に関する規律が妥当することになります。
従来の解釈を明文化
もともと、改正前民法95条の無効は、取消的無効と解釈されていました。
条文上、「無効」と明示されていたものの、解釈上、表意者しかその無効を主張できないなど、その主張適格につき、取消権類似に解されていたのです。
今回の改正民法は、錯誤の効果につき、より端的に、「無効」から、「取消」へと効力を改めたものです。
取消に関する規律(主張適格等)について
錯誤の効果は「取消」となりましたので、改正民法では、取消に関する各種規律が妥当します。
まず、取消というのは意思表示ですので、改正の結果、錯誤を理由に法律効果を打ち消すには、取消権行使の意思表示が必要となります。
また、その主張権者についても制限があります。改正民法120条2項によれば、取消ができるのは、表意者又はその代理人若しくは承継人に限られます。
消滅時効について
また、改正前民法においては、錯誤無効の主張につき、主張期間を5年に制限をすべきではないか、との議論がありました。
取消権の行使について5年とされている一方で、無効については、消滅時効を定める規定がなかったのです(無効であるとの建前であった以上、規定が無かったのは、当然と言えば当然ですが)。
この点に関し、改正民法では、「取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。
錯誤を理由とする取消権も当該規定に従うことになります。
第三者保護規定(善意無過失)の追加
また、改正民法では第三者保護規定が新設されています。
改正民法の下では、取消前に法律上の利害関係を有するに至った善意・無過失の第三者は保護されます。
錯誤における第三者保護
従来、錯誤における第三者の保護をどのように図るのかは解釈上の問題でした。この点を整備したのが民法95条4項です。
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
具体例
たとえば買主Aさんと売主Bさんが不動産売買契約を締結した後、さらにAさんがCさんに不動産を転売していたというケースを想定します。
この場合に、Aさんの転売後にBさんが錯誤を主張した場合、取消の遡及効により、Cさんは無権利者たるAさんから不動産を取得したことになってしまいます。
そうすると、Bさんの取消により、不動産所有権はBさんに戻り、Cさんは不動産を取得できなそうです。
ただ、常にこの結論を維持すると、Cさんの利益があまりに害されます。
そこで、改正民法は、Cさんが善意無過失であれば、取消の効果を対抗できないとして、Cさんの保護を図ることとしました。
無過失まで要求されている
民法95条4項においては、明文で無過失まで要求されている点に要注意してください。
従前の有力説に従う改正ですが、もともと規定のなかったところなのに、第三者の保護要件が割と重たくなっています。
錯誤と損害賠償請求
最後に、関連論点として、表意者の相手方又は第三者からの損害賠償請求について検討します。
相手方からの表意者に対する請求
まず、表意者の相手方が表意者に損害賠償請求をする場面についてです。
結論を先出しすると、不法行為の要件を満たせば、錯誤の相手方は、表意者に対して損害賠償請求をすることが可能です。
問題の所在
表意者の相手方は、錯誤取消をした表意者に損害賠償請求をすることができるでしょうか。これを全く認めないと不都合が生じます。
たとえば、Aさんを買主、Bさんを売主とするケースで、Aさんが「不動産を買う」という意思表示を錯誤により取り消した場合、Bは、Aに対し何らの請求もできないのでしょうか。
たとえば、Bは、売買契約の成立に向けて、仲介業者に仲介費用を支払っているかもしれません、契約書の印紙代を負担していたかもしれません。
Bはこうした費用を負担していたにもかかわらず、Aから錯誤取消(従前民法では錯誤無効)を主張されると、売買による利得は得られず、これまでの手間暇・費用負担がおじゃんになってしまいます。
こうした損害をBはAに賠償して、とはいえないものでしょうか。
請求は可能
上記のようなケースにおいて、BがAに損害賠償請求をすることは可能です。
民法95条のどこにそんなこと書いてあるの?と思われるかもしれませんが、この問題については民法95条をみていても、答えは出ません。
もちろん、民法95条の行間(解釈)にも答えはありません。
根拠規定
根拠となる規定は、民法709条です。
民法709条は、一般不法行為責任に関するルールとして、次のように定めています。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為責任
民法709条の規定の意味は、わざと、又は不注意によって、人の権利や利益などを侵害した者は、その侵害によって生じた損害を賠償する責任とらなければならない、という意味です。
そして、この709条に基づく責任は、債務不履行責任と異なり、契約関係に無い当事者間でも妥当するルールです。錯誤取消(錯誤無効)の当事者間においても、妥当し得ます。
したがって、上記の例では、BはAの過失を主張・立証することで、Aに対して、自己に生じた損害の賠償を求めることができます。
第三者からの請求はどうか。
次に、民法95条4項で保護されない第三者が「表意者」や「相手方」に対して損害賠償を請求できるか、という点について検討します。
結論⇒要件を満たす限り、第三者から、相手方や表意者に対して損害賠償請求をすることは可能です。
ただ相応の過失相殺が予想されます。
問題の所在
改正後民法95条では、第三者保護規定が置かれています。たとえば、買主Aと売主Bの売買後、CがさらにAから不動産の転売を受けたというケースで、後になって、売主Bが錯誤による取り消しを主張したとします。
この場合、Cは、善意無過失であれば保護されて不動産を有効に取得できますが、そうでない限り、不動産を取得できません(改正民法95条4項)。
その場合に、Cは、AやBに対して、損害賠償請求を追及することはできないでしょうか?
以下、私見も混じりますが、この第三者からの損害賠償請求について考えてみます。
債務不履行責任ないし不法行為責任の追及
まず、上記のようなケースにおいては、改正後民法においては、CはAに対して契約の解除を求めることができると解されます。
また、Aに帰責性がないといえなければ、CはAに対して債務不履行責任を問うこともできます。
加えて、AやBに過失があり、Cが当該過失に因って損害を被っていれば、Cは民法709条を根拠に、AやBに対して不法行為責任に基づく損害賠償を行うことが可能です。
過失相殺の対象となりうる
もっとも、第三者から表意者や相手方に損害賠償請求をする場合、相応の過失相殺がなされることが予想されます。
そもそも、錯誤取消の場合において、第三者が保護されないのは、第三者に少なくとも過失がある、とされる場合です(改正民法95条4項)。
これは損害賠償の場面においても問疑の対象となるでしょう。
過失の対象に差こそあり、議論の余地はあるものの、Cが損害賠償請求をする場合、Cは、ある程度、過失相殺されることについても覚悟しないといけないかもしれません。
結論としては、第三者たるCは損害賠償をすることはできるが、一定程度過失相殺されるということになります。