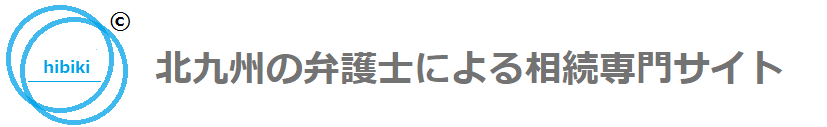今回のテーマは法人格否認についてです。
民法や会社法で出てくる概念ですが、意外と理解が難しい考え方の一つ。法律を勉強し始めた民法の最初の方で出てくるので、混乱しやすいのかもしれませんね。
実務的に問題となることは少ないように思われますが、ここで一応確認しておきましょう。
法人格否認の法理とは
法人格否認の法理とは、①法人格が全く形骸化している場合や、②法人格が濫用されている場合に、紛争や事件の解決のために必要な限度で、法人格を否定する法理を指します。
この法理により法人格が否定された場合、法人と法人の背後にいる支配者との分離が否定されます。
その結果、法人の相手方は、法人の背後にいる支配者に対して責任を追及したり、逆に支配者との間の契約等の効力を法人に及ぼしたりすることが可能になります。
なお、法律的な根拠としては、「信義則」が挙げられることが多いです。
法人格否認の効果
以下、もう少し詳しく見ていきましょう。効果から見た方が、イメージを掴みやすいと思うので、法人格否認の法理の効果から見ていきますね。
法人格の否定
上記の通り、法人格否認の法理は、法人の法人格を否認する法理です。
たとえば、株式会社と契約をしたような場合、契約の相手方は、当然、その会社に対しては契約責任を追及できます。
その一方で、当該会社の代表者(社長個人)は契約の主体(名義人)ではありませんので、契約の相手方は社長個人に対して、契約責任を追及することはできません。
また、株式会社の株主も間接有限責任を負うだけですから(株主は出資する責任しか負わない)、契約の相手方は、当該株主に対しても責任追及をすることができません。
さらに、逆も同様です。社長個人との契約は法人には直接的には及びません。法人と個人とはあくまで別人格だからです。
しかし、上記のような理屈を貫くと、①法人格が全く形骸化している場合や②法人格が濫用されているような場合、実質的な取引や契約の主体等に対して責任をっ追及できず、不都合が生じます。そこで、法人格否認の法理の登場です。
法人格否認の法理が適用される場合、その背後者、上記で言えば会社を実質的に支配する株主に対して責任追及をすることや、本来、支配者に対して請求すべき権利を、法人に直得請求することなどが可能になります。
紛争や事件の解決のために必要な限度でのみ効果がある
法人格否認の法理をもう一度見てみましょう。重要なのはこの法理が「紛争や事件の解決のために必要な限度で」のみ機能するという点です。
たとえば、ある裁判で法人格否認の法理が適用された場合、その裁判でのみ法人格が否定されますが、他の裁判でも当然に、法人格が否認される、という訳ではありません。
この法理は、その適用によって、それ以後における当該法人の法人格を継続的に否定する、というものではないのです。
つまりは、法人格否認の法理には、当該法人を清算させる、あるいは権利能力を否定する、という効力はないことになります。
事件単位・紛争単位で判断される、という点は、誤解しやすいので、是非注意しておいてください。
法人格否認の法理の要件
法人格否認の法理の要件については、次の最高裁判決が参考になります。
最高裁昭和44年2月27日判決
およそ社団法人において法人とその構成員たる社員とが法律上別個の人格であることはいうまでもなく、このことは社員が一人である場合でも同様である。
しかし、およそ法人格の付与は社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであつて、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに、法的技術に基づいて行なわれるものなのである。
従って、法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。
法人格の形骸化・濫用
上記判例をベースに学説においては要件の類型化が図られました。
法人格否認の法理の要件としてよく挙げられるのは、①法人格が全く形骸化していること、あるいは②法人格が濫用されていること、の二つです。
※①あるいは②であって、両者の要件がいずれも満たされていることまでは要求されません。
ただ、事実上、法人格が形骸化しているような場合、同時に法人格の濫用と評価される場合も少なくは無いです。
法人格の形骸化の事例
法人格の形骸化というのは、たとえば株主が社長一人しかおらず、かつ社長個人の財産と株式会社の財産とが混然一体となっており、法人の体裁を取っていても、実体が、社長個人とほとんど変わらないといえるような場合です。
実質、個人事業というほかないような場合がこの例と言えます。このような場合に、法人と社長個人との法人格の区別を貫くと、相手方の保護に欠け、不都合です。
たとえば、上記、最高裁判決は、実質的に個人事業ともいえる株式会社Aを賃貸人とする契約につき、賃借人Bが、その代表者個人Cと不動産の明渡にかかる和解をしたのに、後になって当該会社Aがその和解の効力は会社Aには及ばない、と主張した事案です。
この場合、公平の観点から、代表者Cを信じたBを保護すべき要請が強く働きます。そうでなければBの保護に欠けますよね。
結局、この事案では、法人格が否認され、代表者個人と行った和解が法人にも及ぶと判断されました。
法人格の濫用の事例
法人格の濫用事例というのは、たとえば、法律の適用や債務の弁済を免れるために法人格を濫用するような場合を言います。
たとえば、親会社Aが、不動産を明け渡す義務を負う場合に、不動産の明け渡しを逃れる目的のためだけに、子会社Bを設立して、不動産に係る権利を譲渡し、または占有をさせる等がその例です。
この場合、法人格否認の法理が適用されると、AないしBは、互いに別の法人格であることを主張できなくなります。
これに類する事案として最高裁昭和48年10月28日があります。
このケースは、不動産の明け渡しなどの債務を免れる目的で、新会社を設立して、旧会社の営業財産等を新会社に流用していたという事例です。
最高裁は、当該事例において、新会社は、信義則上、旧会社が別人格であることは主張できない旨の判断を示しています。
実際上の要件に関する私見
要件として類型化されるのは、上記の二つです。ただ、私見ではありますが、実際上の判断に際して、形式的な当てはめがなされることは少ないように思われます。
現実的には、法人格を否認するまでに必要性の有無・強弱、法人格形骸化・濫用の程度、支配者の主観等を総合的に考慮して、法人格の否認の可否(相当性)を判断しているように思われます。
法人格否認の法理は、法人制度の根幹にかかわる法理論ですし、その根拠も信義則ですから、その事件・紛争における法人格否認の必要性や許容性に応じた相当性判断が重要と考えられます。