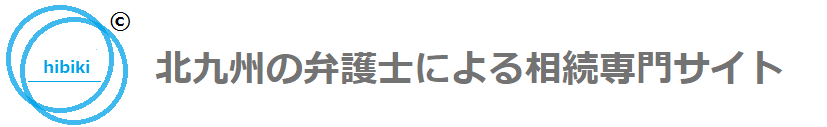今回のテーマは相続・遺産分割協議等と登記具備の要否についてです。
論点チックで申し訳ないのですが、相続持分を勝手に処分されたケース、遺産分割協議が絡むケース、相続放棄が絡むケースをそれぞれ順々に見ていきましょう。
教科書などでは民法177条との関係で論じられることの多いテーマですが、いずれの論点についても、そもそも実際に177条の適用問題となるのか否か、という観点から考える必要があります。
共同相続人の一人が勝手に単独相続の登記をして第三者に処分したケース
一つ目の論点は、共同相続人の一人が、勝手に単独相続の登記をして相続不動産を第三者に譲渡し、第三者において登記も備えた、というケースです。
たとえば、A及びBが共同相続人であり、相続不動産につきそれぞれ2分の1ずつ持分を有しているにも関わらず、Aが勝手に単独の相続登記をして、Cに売却したというケースを想定します。
この場合、他の相続人Bが登記なくして当該第三者に自己の相続持分を主張できるか、が問題となります。
通説の立場は、登記不要説です。Bは登記なくしてCに自らの持分を主張しえることになります。
この通説は、Aは、Bの持ち分につき全くの無権利であることから、そもそもCは有効に持分を取得しえないことを理由とします。
ただ、このように解すると取引の安全が害されえます。そこで、第三者(C)を保護できないかが問題となるわけですが、この点については、いわゆる権利外観法理により保護を図りうる、とされています
上記の論点に関しては、登記必要説もあります。
そもそも共有というのは、数個の所有権が1個の物の上で互いに制限しあって存在している状態である、という前提に立ち、Aは必ずしも無権利とはいえない、という考え方に立ちます。
遺産分割と不動産登記
また、遺産分割をめぐっても、登記の要否が問題となります。
遺産分割前の第三者と不動産登記
まず、遺産分割前に第三者が利害関係を有するに至った場合を考えてみます。
たとえば、AとBが共同相続人であるところ、Bが相続不動産に関しその持分をCに譲渡した後、A及びBが遺産分割協議によってAの単独所有とされた場合を想定します。
この場合に、Cが、Bから譲渡を受けた持分部分について登記なくしてAに権利主張できるでしょうか。
上記の問題に関し適用されるのが、民法909条です。
同条は、遺産の分割の効力が相続開始の時にさかのぼること、ただし、その遡及効によって第三者の権利を害することはできないことを定めています。
もっとも、通説において、民法909条の解釈としては、第三者が不動産に関し自らの権利の保護を求めるためには、登記が必要と解されています(対抗要件ではなく権利保護要件としての登記が必要と説明されます)。
ここでは、相続によって財産を得た者と登記を備えない第三者とを比較して、前者の方が保護すべき要請は高い、という価値判断が働いているものと思われます(私見としては納得しがたいところでもありますが・・・。)。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
これを上記問題に当てはめると、民法909条本文に基づき、Aは、Bとの遺産分割により相続開始の時から、Bの持分部分についても相続していたこととなるが、これをもって第三者の利益を害することはできません。
もっとも、Cとしては、同条但書きの保護を得るためには、権利保護要件としての登記を備えなければなりませんから、結局、Cは権利主張をするためには、登記を備えておくことが必要ということになります。
遺産分割後の第三者と不動産登記
次に遺産分割後の第三者と不動産登記の問題です。
たとえば、AとBが共同相続人であるところ、ABが遺産分割協議により相続不動産をAの単独所有とした後、未登記の間に、Bがその持分をCに譲渡した場合を想定します。
この場合、CはAに対して登記なくして、自己の持分の取得を対抗できるでしょうか
この場合、民法909条但書きの適用はありません。同但書きは、遺産分割の遡及効によって利益を害される第三者、すなわち遺産分割前の第三者を保護する規定と解されるからです。
もっとも、遺産分割協議による持分の移転と、持分の第三者への譲渡はいずれも、共同相続人の一人の意思に基づくものですから、持分が二重に譲渡された関係と類似します。
そこで、通説は、登記必要説をとります。Bの持分部分につきAとCとが対抗関係に立つと考えるわけです。
判例も登記必要説に立っています。
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものである」
「不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法一七七条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」
177条の理解については関連記事をご参照ください。「対抗関係」の意味や同上の訴訟における攻撃防御方法としての位置づけなどについて解説しています。
相続放棄と不動産登記
最後に相続放棄と不動産登記に関する論点を確認しておきます。
たとえば、共同相続人A及びBが相続不動産につき、それぞれ2分の1ずつの持分を有していたところ、Bが相続放棄をした後、相続登記未了の間に自己の持分をCに売却してしまった、という場合を想定します。
この場合、Cは有効に権利を取得するでしょうか(ACは対抗関係にたつでしょうか)。
相続放棄の効力は絶対的
そもそも、相続放棄というのは、相続資格者が相続を放棄することによって、初めから相続人ではなかったことになるという仕組みです。
そして、この効力は絶対的なもの(ある者との関係で効力が生じたり、生じなかったりする相対的なものではない)と解されます。
相続放棄との対比にいて遺産分割の遡及効には、但書きにより第三者の権利を害することができないとの制限が付されたが、相続放棄についてはこのような制限が加えられていません。
この規定の違いに照らしてみても、民法は相続放棄の遡及効については絶対的効力を認めたものと解されるわけです(後掲最判昭和42年1月20日判決調査官解説参照)。
これを上記事例にあてはめれば、Bは相続放棄によって相続開始の時から無権利であったことになります。そして、その効力は絶対的です。したがって、Cは無権利者から持分の譲渡を受けたにすぎないものと観念されます(有効に権利取得できません)。
それゆえ、ACは対抗関係に立たず、Aは、登記なくして、Bの持分部分につき、その権利をCに対抗することができます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
判例の立場
なお、上記の論点についても、最高裁の判決があるので、引用しておきます。
相続放棄に関し「民法が承認、放棄をなすべき期間(同法九一五条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法九三八条)、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである。」