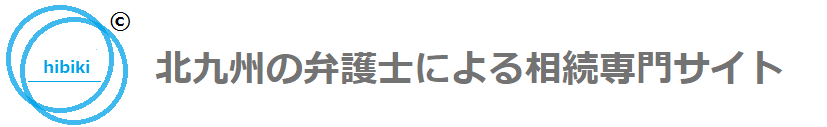今回のテーマは、民法177条についてです。
この規定は不動産の物権変動の対抗要件について定めた規定です。
日常の取引において、この177条が正面切って登場することはあまり無いかもしれませんが、「物権法」を理解する上では最重要の条文の一つです。
大学の民法の試験や各種の資格試験対策という意味でも極めて重要です。
以下、この規定の意味、機能する場面、いわゆる「第三者」の解釈などをそれぞれ見ていきましょう。
民法177条の規定
はじめに条文を確認します。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この条文のタイトルからもわかる通り、この規定は不動産物権変動の対抗要件について定めた規定です。
「所有権を得た」とか「抵当権の設定を受けた」など、物権の変動につき、「登記」がないと対抗できないものと定め、「登記」を対抗要件としているのです。
たとえば、AさんがBさんから不動産を買った場合、その売買によって所有権を得たことを第三者に対抗するためには、登記が必要ですよ、と言っているわけです。
以下、民法177条の文言中、まず、次の2点をそれぞれ簡単に見ていきます。
・「不動産に関する物権の得喪及び変更」(物権変動)
・「登記をし」(登記具備)、
そのうえで、「対抗することができない」の意味を確認し、最後に、同条の解釈で最も重要な「第三者」の意義について解説していきます。
「不動産に関する物権の得喪及び変更」(物権変動)について
上記177条の主語は、「不動産に関する物権の得喪及び変更」です。
これを物権変動と呼びます。不動産に関する物権にかかる権利の発生や消滅、変化のことです
典型例は、上記に挙げた所有権の移転ですが、その他、地上権などの用益物権の設定や消滅、抵当権の設定や消滅などもここに含みます。
上記のとおり、民法177条は、「不動産」の物権変動について定めた規定です。「動産」には適用がありません。
宝石や絵画などの動産については、別途178条が「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と定め、引き渡しを対抗要件としています。
登記の具備について
民法177条によれば、物権変動を第三者に対抗するためには、登記をしなければなりません。つまり、登記の具備が対抗要件となります。
誤解を恐れずにいえば、登記具備というのは、法務局で取り扱われる登記簿に不動産権利関係を登録することを指します。
民法177条は、この登記具備がないと、物権変動は、第三者には対抗できませんよ、と言っているわけです。
たとえば、相続などがあって「家の名義を変える」、というような場合や、親から子供に「土地所有者の名義を変更しておこう」等という場合の多くは、登記上の権利者を変更しようという意味合いになります。
この登記のイメージが付きにくい方は、一度法務局へ行って、自分が住んでいる家の登記事項証明書を取ってみるといいです。
そこには、その家の所有者が記載されている(建物を賃借している場合にはオーナーなどの名前が記載されています。)はずです。
「対抗できない」とは
次に民法177条が定める「対抗できない」の意味を見てきましょう。
なお、この「対抗できない」の部分は、法律の「効果」を定めた部分ですから、本来であれば、要件論である「第三者」を先に説明すべきかもしれません。
ただ、「第三者」論については説明することがたくさんありすぎますので、後でまとめて説明します。
物権変動の主張が排斥される
民法177条の文言にある「対抗できない」との意味は、大ざっぱに言えば、自分が権利を取得した等と第三者に「主張することができない」、という意味です。
主体を変えて言えば、第三者側から、「登記を備えていない者の権利主張を排斥できる」、ということになります。
第三者側から、「あなた、自分が権利を得たって言っているけど、登記はあるの?ないんでしょ?じゃぁ、だめだめ、あなたのそんな主張、こちらは知ったことではないよ」などと言える、わけです。
唐突ですが、これをサッカーのチケットにたとえてみましょう。
サッカーの試合のチケットを買ったと主張する人が、そのチケットを持たずに会場に来た場合に、主催者側はどう対応するでしょうか。
この場合、主催者側は、「ダメダメ、チケットがないと入れないよ。」と入場を規制するはずです。
その人が現にチケットを買ったかどうかに関わらず、チケットを持っていないと、試合会場には入れなくなります。
177条の適用もこれに似ています。
その人は現に権利を得たのかもしれないけど、第三者側は、「登記が備えられていない」という事実(これを登記の欠缺といいます。)をもって、その権利主張を排斥できるわけです。
登記の欠缺は抗弁に回る
上記のように、「対抗できない」の意味は、物権変動の主張を第三者に主張できない、という意味ですが、裁判などの場面では、登記の欠缺は、抗弁事実に回ります。
民事訴訟法の知識がないと少し難しいかもしれませんが、重要なことなので説明をしておきます。
「抗弁事実に回る」ということの意味は、第三者側が登記の欠陥を主張することになる、という意味です。
たとえば「Aさんが権利を得た」と主張する場合に、Aさんは売買などで所有権を取得した、と主張・立証することになります。
これに対して、177条は、その権利取得者の主張を否定したい第三者側が「いやいや、Aさん登記を具備してないよね、登記を欠いていますよ」と反論できるよ、と定めているものと理解されるのです。
なお、登記の欠缺が抗弁事由に回ることからすれば、「対抗できない」の実質的な意味合いは、第三者側の視点から位置付ける方がイメージしやすいかもしれません。
つまり、「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」の意味を、登記の欠缺をもって、第三者側が、権利取得を主張する者の権利取得の主張を排斥できる、という視点で考えるわけです。
これは、互いに登記が備わっていない場合には、互いに相手の主張を排斥できる、という意味になります。
くどいかもしれませんが、もう少し補足します。私が学生の頃、この177条を勉強している際に、よく引っかかっていたのが、この「対抗することができない」という法律効果の位置づけです。
この点につき、民法の教科書などでは、「登記を備えた方が勝つ」などと記載されています。実体的に見れば、対抗関係が生じる場面では、登記を備えた方が勝つ、という考え方で確かに間違いありません。
しかし、既に述べた通り、登記の欠缺は、第三者側から見たとき、権利取得者の権利取得の主張を排斥するための抗弁事由に回ります。
つまり「登記を具備したこと」ではなく「登記を具備していない」(登記の欠缺)が、権利取得者の主張に対する法的な反論になるとわけです。
そうだとすれば、民法の教科書を眺めて、「登記を備えた方が勝つ」というイメージで民法177条をとらえるよりも、訴訟などを意識して、「登記を備えていないと第三者にはまける」というイメージの方が、同条の理解はすすむのでないかと思います。
そして、このように考える場合、次に述べる「177条の第三者」に当たるかという議論は、実質的には、権利取得者の登記の欠缺を主張することが、抗弁になるのかならないのか、という点を左右する意味合いを有するものと言えます。
第三者に当たれば、登記欠缺が抗弁になるし、第三者に該当しなければ登記欠缺が抗弁にならない、そのために、ある者が第三者に当たるか否かが訴訟の帰趨を左右する重要な解釈事項になる、ということです。
民法177条の第三者とは?その範囲について
さて、いよいよ民法177条の中心的解釈事項となる「第三者」についてです。
もう一度、条文を見ておきましょう
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
上記のとおり、この規定は、物権変動につき、登記なくして「第三者」に対抗できないと定めるものです。
これを裏から読むと、物権変動であっても「第三者」に該当しない者については、登記失くしても物権変動を対抗できる、と解することが可能です。
そのため、ある者が民法第177条の「第三者」に該当するか否かで、その者に対して、権利取得者等が登記なくして権利取得などの物権変動を対抗できるのか否かが異なってきます(訴訟レベルにおける位置づけについては上述の補足参照)。
そこで、この「第三者」の範囲をどのように理解するかが重要な問題となります。
無制限説と制限説
上記第三者の範囲に関し、判例はかつて、無制限説をとっていました。
物権変動の主体たる当事者やその包括承継人以外の者はみんな第三者に当たるとの解釈が取られていたのです。民法177条が単に「第三者」と記載しているだけで、ほかの留保をつけていないことからすると、無制限説の解釈は条文に忠実と言えます。
しかし、この無制限説に立つ場合、不法占有者なども第三者に該当します。つまり不法占有者等も登記の欠缺を主張することで、権利取得者等の権利主張を排斥できるという結果となります。この結論が妥当性を欠くのは明白です。
そこで、判例は、第三者につき立場を改め、制限説を採用しました。第三者に該当する者を一定の範囲に制限する考え方です。
具他的には、判例は民法177条の定める第三者につき、「当事者及び包括承継人以外の者で,不動産の物権変動について登記の不存在(欠缺)を主張するにつき正当な利益を有する者をいう」と判示し、第三者の範囲を「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」に限定したのです(大判明41.12.15、最判昭25.12.19等参照)。
上記の不法占有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しませんので、第三者には該当しないことになります。
また、一般債権者や、実質的な無権者、詐欺又は強迫によって,登記の申請を妨げた者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない(第三者には該当しない)と解されています。
いわゆる背信的悪意者(後述)についても同様です。
なお、いうまでもなく、不動産の売買における売主は、買主との関係で第三者には当たりません。
不動産の売主は、買主との関係で「当事者」にすぎず、両者は前主・後主の関係にたつにすぎないからです。
ここで「対抗関係」という言葉について説明します。
対抗関係というのは、ある物権につき、互いに相反する権利を有するため、相互に食うか食われるかという立場に立つ関係を指します。
制限説を前提に、民法177条の第三者論に引き直して言えば、互いに相手の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する関係ということになります。
お互いに正当な利益を有するところ、その優劣を登記をもって決めようぜ、という関係に立っていることを「両者は対抗関係に立っている」と表現するわけです。
民法177条と二重譲渡
上記の制限説の下で、民法177条が働く典型的な場面は、不動産の二重譲渡の場面です。
たとえば、AがBに土地を譲渡し、登記移転をしないまま、AがさらにCに同じ土地を譲渡したという場合などです。
二重譲渡の場合の対抗関係~不完全物権変動説~
上記のような事案で、そもそも問題となるのは、Cが登記の欠缺を有する正当な利益を有するのか、つまりAとCは対抗関係に立つのかという点です。
ここでは、AからBに土地が譲渡された場合、その時点でAは無権利となるため、Cは無権利者から譲渡を受けたにすぎず、Cも無権利なのではないか、正当な利益を有しないのではないか、という点が問題となるのです。
この点に関し、通説的な地位を占めているのは、AがBに不動産を譲渡したとしても、その物権変動は不完全であり、排他性を備えない、という考え方です。
この考え方の下では、後に不動産を譲り受けたCも不完全ながらも所有権を取得する、そのため、Cも登記の欠缺を主張しうる正当な利益を有する「第三者」に該当する、と考えることになります。
つまり、AもCも、不完全ながら、権利性を有するので、互いに登記の欠缺を主張する正当な利益を有することになります。
そのため、両者は対抗関係に立ち、その優劣は登記具備の先後によって定まることになります。
完全物権変動説に対しては、技巧的にすぎるのではないか、民法176条は、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示「のみ」によって、その効力を生ずる。」と定めているのに、登記によって排他性が備わる、というのはどういうことか、個人的には疑問がないではありません。
他方、この点は学術的な色彩の強い議論でしょうから、端なる資格対策や実務において深入りする必要性はそれほどないとも思っています。
個人的には、疑問はあるにせよ、勉強の際には、不完全物権変動説は、二重譲渡をどのように説明するのか、説明の仕方の問題と割り切るのもアリだろうと思います。
第二譲受人が悪意の場合
では、第二譲受人が第一譲渡につき悪意の場合(知っていた場合)はどうでしょうか。
上記の事案に引き直すと、Cが、AのBに対する譲渡を知りながら、Aから不動産の譲渡を受けた、という場合です。
この場合、BとCが対抗関係に立つか、つまりCがBの登記の欠缺を主張しうる正当な利益を有すると言えるかが問題となります。
この点に関し、判例・実務は固まっています。
そこでは、第二譲受人が単に第一譲受人への譲渡を単に知っていたというだけの場合、第一譲受人と第二譲受人はやはり対抗関係に立つ、という考え方が採用されています。
つまり、第二譲受人は悪意であってもなお、登記の欠缺につき正当な利益を有する第三者に該当すると判断されます。
これは、第一譲渡を知っていたにすぎない場合にさらに譲渡を受けるのは、依然として自由競争のとして許容されるべきという価値判断によるものです。
第二譲受人が背信的悪意の場合
では、単なる悪意を超えて、自由競争としても許容できないような強い背信性が第二譲受人にある場合はどうでしょうか。
たとえば、登記がないことをいいことに、第二譲受人が他人を害する目的で物権を取得したような場合です。
さすがに判例もこのような場合にまで、第二譲受人に登記の欠缺を主張しうる正当な利益があるとはいいません。
判例の立場においても、自由競争の観点からみても第二譲受人の利益を保護すべきという価値判断が働かない場合、第二譲受人は「登記の欠缺を主張しうる正当な利益」を有しないと判断され得ます。
つまり、背信性を有する悪意者(背信的悪意者)として、対抗関係から排除されるのです。これを背信的悪意者排除論といいます。
たとえば、AさんがBさんとCさんに不動産を二重譲渡したという場面で、Cさんが背信的悪意者である場合、Bさんは、登記なくして自己の物権変動を主張できます。
逆に言えば、Cさんは、Bさんの登記の欠缺をもってBさんの主張を排斥できない、ということです。
二重譲渡と177条の簡単なまとめ
背信的悪意者排除論まで含めると、二重譲渡の場面における対抗関係の成否は次のように整理されます。
①二重譲渡の場面において両譲受人は、基本的に対抗関係に立つ
②第二譲受人が単に悪意であっても同様(第三者に該当する)
③但し、第二譲受人が背信的悪意者と言える場合、第二譲受人は民法177条の第三者には該当しない(第一譲受人との関係で対抗関係に立つことが否定される。)。
取消後の第三者
民法177条が機能するのは、二重譲渡の場面に限られません。
民法の世界では、この177条をめぐり詐欺などによる法律行為が取消された後に現れた第三者が同条の第三者に該当するか、という有名な論点があります。
この問題は、たとえばBさんがAさんをだまして不動産を詐取し登記を得た後、Aさんが当該不動産の処分にかかる意思表示を取り消した、しかし、Aさんが登記名義を取り戻す前に、BさんがさらにCさんに不動産を売ってしまった、という場合に生じます。
では、上記事例において、Bさんから不動産を取り戻したいAさんと、Bさんから不動産を買い受けたCさんとは対抗関係にたつでしょうか。
いいかえれば、Cさんが登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者といえるか、が問題となります。
なお、詐欺取消前の第三者等については、それぞれの条文が定める保護要件を満たすか否かによって、原所有者が優先するのか、第三者が権利取得するのか、が判断されます。
民法94条2項の類推適用により対応すべきとする説
上記の点に関し、取消後に現れた第三者は、無権利者から不動産を買ったにすぎないから、やはり無権利である、そのため、取消をした原所有者と取消後に現れた第三者とは対抗関係に立たない、という考え方があります。
上記の事例に引き直して言えば、Aさんの取消により、Bさんは遡及的に無権利となるから、CさんはBさんから不動産を買ったとしても、所有権は移転しない、と考えるのです。
もっとも、このような場合にBさんが全く保護されないとすればBさんにあまりに酷ですから、この見解は権利外観法理を基礎に置く民法94条2項を類推適用してその保護を図ろうとします。
すなわち、取消後の第三者(上記事例ではB)が善意(乃至善意又は無過失)である場合には、取消後の第三者側が保護されると考えるのです。
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
権利外観法理について解説した記事です。帰責性と立証責任の関係などについても解説しています。
取消後の第三者と177条
しかし、民法94条2項を類推適用する見解は、通説化はしていません。
判例は次に述べる通り、復帰的物権変動という考え方を採用します。
復帰的物権変動論
判例は、上記原所有者と取消後の第三者は対抗関係に立つとします。
つまり、取消によって、原所有者に復帰的に物権が変動する一方で、取消後の第三者は相手方から物権を取得しているのであるから、二重譲渡類似の状況であるとして、両社が対抗関係に立つ、という考え方をとります。
上記事例に引き直して言えば、取消によってBさんからAさんに所有権が復帰的に移転する一方で、Bさんは不動産を買っているのであるから、Bさんを起点とする二重譲渡類似の関係が成立する、と考えることになるわけです。
この考え方によれば、AさんとCさんとは対抗関係に立ち(互いに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する)、その優劣は登記の先後で定まることになります。
この判例の考え方は、取消の遡及効を貫徹していないのではないか、と批判されることもありますが、原所有者Aも、不動産を買い受けたCも、どちらにも正当な利益がある、という価値判断からすれば、この判例の考え方にも理由があると言えそうです。
なお、Cが悪意で、かつ背信性がある場合には、背信的悪意者論を応用することで結論の妥当性を維持することも可能と思われます。
たとえば、Aさんによる詐欺取消の後、事情を知ったCさんが、Bさんの便宜を図る趣旨でBさんから不動産を譲り受けたという場合には、Cさんを背信的悪意者と評価することで、Aさんの保護を図ることが可能でしょう。
Aが詐欺されたことまでCが知っているとの事情がある場合、背信性が肯定される可能性は高いのではないかと思います。
処分禁止の仮処分
ところで、上記事例でAさんがBに対して意思表示の取消を前提に登記名義を移転せよ、という裁判を起こした場合、裁判継続中にBさんがCさんに不動産を処分してしまう、という事態が生じ得ます。
177条で処理する判例の立場を前提とすればCさんに処分されてしまった場合、Aさんは基本的に敗訴となります。対抗関係で負けるからです。
そこで登場するのが不動産の処分禁止の仮処分です。Bさんが不動産を処分することを禁止する命令を裁判所から得るのです。
ただ、仮処分を得るには少なくない費用が掛かりますから、簡単に仮処分を取っておけ、とは言いにくいところではあります。
しかし、リスクを勘案するならば上記のようにAさんからBさんに対して裁判を起こす場合、Aさんにおいては、Bさんに対する不動産禁止の仮処分を得ておくべきではないか、十分検討しておくことが重要になります。
解除後の第三者
上記において、詐欺などを理由とする取消後の第三者が登場するケースにつき解説しましたが、同種の問題は、取消の場面だけでなく、解除の場面でも登場します。
例えば,AさんがBさんに不動産を売って登記を移転したところ、Bさんが売買代金を支払わないので、Aさんが契約を解除した、しかし、Aさんに登記が戻る前にBさんはCさんに不動産を売ってしまった、という場面で上記問題が生じ得ます。
結論を言えば、原所有者と解除後の第三者は、対抗関係に立ちます。
この点、取消の場面と同様、「解除の遡及効を貫徹した上で、第三者の保護は94条2項を類推適用して図る」という見解(94条類推適用説)も有力ですが、判例はやはり対抗関係の問題として処理します。
つまり、原所有者と解除後の第三者につき、二重譲渡類似の関係に立つことから、登記を先に具備した者が優先すると解するのです。
上記事例でいえば、やはりBを起点とするAへの復帰的な物権変動と、BのCに対する譲渡を二重譲渡類似のものと考えることになります。
なお、この場合において、Cが登記を先に備えたが、実はCに背信性があったという場合はどうでしょうか。
この場合には、やはり背信的悪意者論を応用することで、解決の妥当性(Aの保護)を図ることが可能と思料されます。
たとえば、Cが解除の事実を知りながら、Bの便宜を図るためにあえてBから不動産を買い受けたという場合、Cを背信的悪意者として民法177条の第三者には該当しない、と考えるわけです。
では、解除前に現れた第三者はどうでしょうか。
たとえば、AがBに不動産を譲渡したところ、Bがさらに当該不動産をCに譲渡した後、AがBの債務不履行を理由に契約を解除した、というケースを想定します。
この点に関し、民法545条1項ただし書きは、解除は「第三者の権利を害することはできない」と定めています。
この規定は、解除の遡及効によって利益を害される第三者を保護する規定ですから、解除前の第三者(遡及効によって利益を害される第三者)の保護は、この規定によることになります。
もっとも、契約の解除につき、原所有者に何らの帰責性がない場合もあることからすると、解除前の第三者であれば、無条件に保護されると解するのは、原所有者に酷です。
そこで通説は、解除前の第三者が545条1項但し書きの第三者として保護されるためには、権利保護要件として登記を備えることが必要と解しています。
※なお、判例は、解除前の第三者が545条1項ただし書きの「第三者」として保護されるためには「対抗要件としての登記」が必要と判示していますが(大判大10.5.17参照)、この点については、解除前の第三者は解除後の第三者の場合と異なり、対抗問題とはならないのではないか、と強く批判されています。
177条の論点はまだまだある
以上、民法177条に定める次の各文言に関する解釈上の説明を行ってきました。
・「不動産に関する物権の得喪及び変更」
・「登記をし」(登記具備)
・「対抗することができない」
・「第三者」
上記の内、特に第三者をめぐっては、二重譲渡にかかる不完全物権変動論、背信的悪意者論につき説明し、取消・解除後の第三者をめぐっては復帰的物権変動論などについて解説してきました。
これらの諸論点は177条の適用場面を考えるための極めて重要な素材です。
ただ、民法177条に関連する論点はこれだけではありません。むしろ、本記事は、177条に関する法律問題の内、どちらかというと基本的な問題を扱うものです。
具体的には民法177条をめぐっては、まだまだ、次の関連記事にて述べたような問題が残っています。特に背信的悪意者論は、基礎知識としても重要です。
<背信的悪意者論について>背信的悪意を認定できるのはどのような場面か、背信的悪意者からの転得者は対抗関係に立つかなどを解説
<民法177条と時効の問題>時効完成前の第三者・時効完成後の第三者は時効によって権利取得される者との関係で対抗関係に立つか、時効取得との関係で、背信的悪意者における「悪意」を判例がどのように解しているかなどを解説。
遺産分割後の第三者と相続人は対抗関係に立つか、相続放棄の場合はどうか、などを解説した記事です。