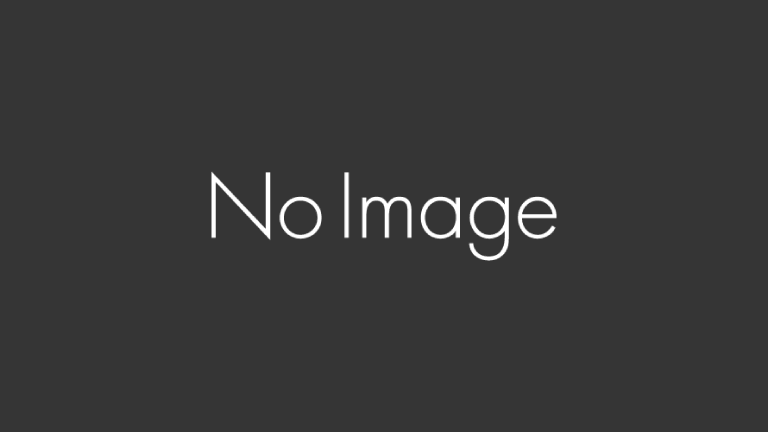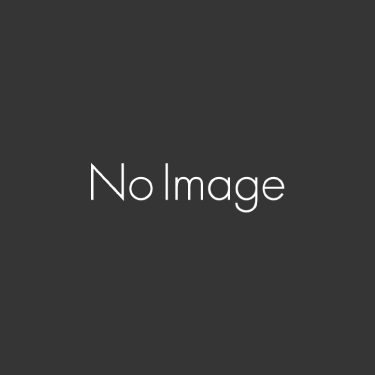今回は、民法の代理の要件の一つである「顕名」についてです。
顕名の読み方は「けんめい」です。
以下、代理の要件としての顕名につき法律上の定義や意味等を確認していきます。
顕名とは
顕名とは、代理人が本人のためにすることを示す行為をいいます。
民法の代理においては、「顕名」が本人に法律行為の効果を帰属させる重要な要件となっています。
代理人が代理して行った契約を本人に帰属させるためには、原則として、当該契約を誰のために行うのか、相手方に明らかにしなければならなりません。
なお、「顕」という字は、一文字で、「明らかにする」とか「目立つ」などの意味を持ちます。
また、「顕名」という熟語における「名」は、効果帰属する本人の名前を意味します。
そのため、顕名という熟語は、本人の「名」を「明らかにする」、という言葉の成り立ちにおいて理解することができます。
顕名主義
代理行為の効果を本人に帰属させるために原則として顕名を要するという考え方を「顕名主義」といいます。
民法99条は、その文言において、「本人のためにすることを示してした」ことを代理の要件としており、顕名主義をとることを明らかにしています。
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
一般的な顕名の方法
代理人が本人のためにすることを示す一般的な方法(一般的な顕名の方法)としては、次のような表記法があります。
「A代理人B」
これは、BがAの代理人として、Aのために契約をすることを示す顕名方法です。
契約書等において、たとえば、A代理人B㊞などと署名・押印します。
また、法定代理人であれば、たとえば次のような記載方法が考えられます。
「A法定代理人後見人B」
これは、Bが後見人の立場たる法定代理人として、Aのために契約をすることを示す顕名方法です。
契約書等において、たとえば、A法定代理人後見人B㊞などと署名・押印します。
上記以外の方法
顕名主義は、代理人が「本人のためにすることを示してした」との要件の充足を求めるものにすぎません。
そのため、相手方にとって、代理人が本人のために契約をしているのだ、と分かれば、必ずしも上記のような記載方法によらなくても、顕名の要件は充足されます。
たとえば、ある契約書において、顕名の方法として「B㊞(Aを本人とする代理人として)」などと記載した場合であっても、Bが本人Aのために契約をしていることが相手に伝わりますから、顕名の要件は充足されます。
メルクマールは、代理人が本人のためにすることを相手が理解できるような記載がなされたか否かであって、記載方法自体には、いろいろなパターンが考えられます。
顕名は口頭でも可能。
立証の問題を一旦措くとすれば、顕名は、口頭でもかまいません。民法は、顕名を文書ですることまで要求していないからです。
たとえば、Aの代理人として契約するね、と相手に口頭で伝えておけば、それをもって顕名の要件は充足されます。
顕名を欠く場合と顕名主義の例外
上記の通り、顕名は、民法における代理の要件の一つです。では、この要件を欠いてしまった場合はどうなるのでしょうか。
顕名を欠く場合
民法100条によると、この要件を欠く場合、当該代理行為の効果は、直接本人に帰属せず、代理人に帰属してしまうのが原則となります(同本文。なお条文については後掲)。
たとえば、Bが買主Aの代理人として売買契約をしようとした際、顕名を欠いてしまったとしましょう。
この場合、上記原則に従えば、Bは、売買代金を相手方に支払う義務を負います。売買契約の効果が代理人たるBに帰属するからです。
顕名主義の例外
他方、民法100条は、顕名を欠いた場合であっても、例外的に本人に効果帰属する場合があることを定めています。
具体的には、代理人が本人のためにすることを相手方が知り、又は知ることができたときは、顕名を欠く場合でも、本人に代理行為が効果帰属します。
代理人が本人のためにすることを相手方が知り又は知ることができたような場合、顕名の趣旨(代理人が本人のためにすることを相手において理解させる)が実質的に充足されているといえるからです。
たとえば、Bが買主Aの代理人として売買契約をしようとした際、相手方が、BがAのために売買契約をしようとしていると知っていた又は知ることができた場合には、同売買契約の効果は、Aに帰属することになります(民法100条但書)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
商事代理と顕名
なお、上記の説明はあくまで民法の代理に関する説明です。商人間の代理行為については、そもそも顕名主義が採用されていません。
商事代理においては顕名なく本人に効果帰属する
商行為としてなされた代理行為は、顕名なくしてなされた場合であっても、直接、本人にその行為の効果が帰属します(商法504条本文)。
商行為の代理の場合、相手方において本人たる営業主を知っていることが通常であること、本人が営業主であることを相手方において通常期待していると考えられるからです(504条本文の実質的な根拠)。
代理人への履行請求
但し、例外的に、相手方が、代理人が本人のためにする行為であることを知らなかった場合(その立証責任は相手方にある)には、相手方は、代理行為が代理人に対し履行の請求をすることが可能です(商法504条但書)。
この場合には、上記504条本文の上記実質的根拠がもはや妥当せず、代理人たる人物に対して履行請求することが、相手方において契約時に想定されていたとも考えられるからです。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
署名代理
以上、顕名に関する法律上のルールを確認してきましたが、最後に、署名代理といわれる論点について若干言及します
署名代理とは
署名代理とは、代理人が代理人であることを明らかにせず、本人の名前のみを用いて代理行為をすることをいいます。
そんなこと実際にあるのか、とも思われるかもしれませんが、社会一般では、代理人が代理人として行動する場合であっても、契約書の作成等について、本人の名前のみを記載するというケースが往々にしてあります。
任意代理の場合はさすがに少ないでしょうが、法定代理においてはしばしばみられる事象です。
署名代理と顕名
上記のような場合、契約書には、代理であることが示されておらず、本人名しか書かれないことになります。これで、代理における顕名の要件を満たすといえるか否かが、署名代理の論点です。
なお、契約書に本人名のみ記載した、という場合であっても、口頭で、本人の代理人であることを示していれば、顕名の要件は充足します。
そのため、厳密には、口頭でも文書でも、代理人であることが示されていない(あるいは代理人側において口頭顕名した旨の立証ができない、という場合に問題となります
署名代理の有効性に関する考え方
この署名代理の有効性に関しては種々の考え方がありますので、本記事では、考え方を紹介するにとどめます。
内田先生の教科書の記述
一つの考え方としては、東京大学出版会民法I(総則・物件総論)内田貴[著]の記述が参考になります。
相手方としては契約の相手について正しく情報を得ているのだから、特別な場合を除き(相手の人柄が重要な契約で,行為者が本人だと信じて,それを見込んで契約した場合など),顕名主義に抵触せず、代理行為は有効とされている。
ここでは原則有効とされています。
Sシリーズの記述
他方で、有斐閣Sシリーズ民法Ⅰ-総則(第3判補訂)(山田卓夫・河内宏、安永正昭・松久三四彦著)では次のように説明されています。
代理人がいきなり本人の名前で行為をした場合も、事情によっては、適法な代理があったと解されることがありうる。
Sシリーズのほうでは、原則論として明確に有効とはされていません。
いずれの教科書においても、有効な代理となりうる場合がありうることを前提としていますが、原則有効とする内田貴先生の記述と、「事情によっては、適法な代理があったと解されることがありうる」とするSシリーズとの解説では、ニュアンスが若干異なります。
この点、どのような考え方に立つべきか確たる基準はありません。
ただ、いずれにおいても、本当に当該代理を有効とすることが相手方保護に欠けることはないのか(内田先生の記述におけるカッコ書部分の考慮や、Sシリーズにおける「事情」の考慮)を検討することが実質論としては重要になります。