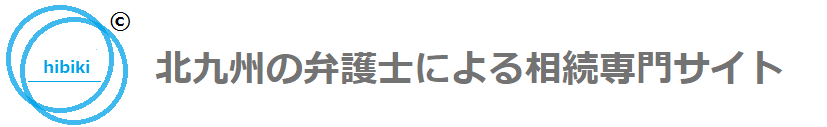今回のテーマは「無権代理人と相続」についてです。民法総則の教科書に必ず出てくる重要論点の一つですので、ここで抑えてしまいましょう。
以下、本記事では、本人が無権代理人を相続した場合を先に説明し、次に、無権代理人が本人を相続した場合について説明します。それぞれ、関連論点がありますので、併せて記載します。
論点チックであまり面白くはないかもしれませんが、ご容赦ください。
本人が無権代理人を相続した場合
まず、本人が無権代理人を相続した場合について考えてみます。
この場合において、本人と無権代理人の両者の地位は、いずれも同一人物に帰属することになります。
では、その両者の地位は一体どうなってしまうのでしょうか。
代表的な二つの見解
この点につき、代表的な理論としては、両者の地位が一体となる、という理論(地位同化説)と、両者の地位が、同一の人格において併存するにとどまるという理論(地位併存説)の二つがあります。
地位同化説による場合
地位同化説は、同一人格の中で、本人と無権代理人の地位とが同化し、無権代理は有権代理になる、という見解です(我妻先生)。地位融合説と呼ばれる見解もこれに類する見解です。
この地位同化説は、同一人格において、両者の地位が帰属した場合、有権代理構成となりますので、本人が無権代理人を相続した場合、本人に無権代理人の行った代理行為の効果が有効に帰属します。
そのため、本人は追認拒絶権を喪失します。
地位併存説による場合
地位併存説は、両者の地位が同一人格に併存するという見解であり、相続が生じても、相続前の無権代理は、あくまで無権で行われた行為にすぎない、という前提に立ちます。
この場合、無権代理人を本人が相続したとしても、相続前に行われた無権代理行為は、あくまで無権で行われたものにすぎず、その効果は、本人の追認によってはじめて有効に本人に帰属します。
反対に、本人が追認を拒絶することも可能です(最判昭和37年4月20日参照)。
無権代理人の地位を相続した本人が追認拒絶する点に関して、追認拒絶したって、本人は結局無権代理人として履行責任を負うのだから、意味ないじゃないか、と思われる方がいるかもしれません。
学生自体の私もそうでした。また、同種の問題意識から、無権代理人の履行責任の範囲を限定すべきとする見解も有力です(ただ、個人的には、条文の文言に照らして、無理を感じる)。
しかし、そもそも、無権代理人の責任について規定した117条2項を確認してください。無権代理人が免責される場面が3つ設定されています。
117条2項各号が定める要件が満たされれば、無権代理人を相続した本人も、無権代理人の責任を免れえるのです。
つまりは、本人は、無権代理人の地位に基づいて、必ず履行責任を負う、とは限らないわけで(なお、同2項の要件が満たされれば、損害賠償責任も免れる)、追認拒絶の意味がなくなるわけではありません。
民法117条の規定については、関連記事にて、紹介・解説をしていますので、ぜひ一度ご確認願えれば幸いです。
無権代理に関し、民法113条~118条までを詳しく解説しました。そもそも無権代理の要件・効果が気になる方は、先にこちらをご参照ください。
一部追認や一部追認拒絶の可否など、教科書ではあまり触れられていない問題についても解説しています。
第三者が本人を相続し、その上で無権代理人を相続した場合
次に、第三者がまず本人を相続し、その上で無権代理人を相続した場合を考えてみます。
この場合、意識すべきは時系列です。
構造上は、第三者が本人を相続した時点で、第三者は本人の包括承継人として、本人の地位を取得したものと扱われます。
そして、その後において、当該第三者はさらに無権代理人たる地位を相続したにすぎません。
そのため、この場面は、時系列を整理すれば、本人たる地位を有する第三者が無権代理人を相続した、という場面になります。
そうだとすると、これは結局、本人が無権代理人を相続した構図と同一の構図となりますから、結論としても、本人が無権代理人を相続した上記の場面と同様になる、と考えられます。
無権代理人が本人を相続した場合
上記は、本人が無権代理人を相続した場合でしたが、反対に、無権代理人が本人を相続した場合はどうなるのでしょうか。
まず、①無権代理人が本人を単に相続した場合、②無権代理人が本人を相続したが、本人が生前に追認拒絶していた場合を考えてみましょう。
そのうえで、上記①の亜種として、③第三者が、まず無権代理人を相続し、その上でさらに本人を相続した場合を考えてみます。
①無権代理人が本人を単に相続した場合
まず、地位同化説に従えば、相続により、無権代理人と本人の地位が同化され、有権代理として扱われますので、無権代理行為は、有効に効果帰属します。
他方、地位併存説に従えば、無権代理はあくまで無権にすぎません。そのため、同説の考え方を貫くと、本人の地位を相続した無権代理人は、本人の地位に基づいて、効果帰属を否定できます(追認拒絶)。
ただ、無権代理行為を行った無権代理人が、本人を相続したことを奇貨として追認を拒絶できるとするのは信義に反しえます。
実際問題、相手方からすれば、「お前あのときは勝手にやっておいて、いざ自分のこととなったら、拒否するのかよ」と言いたくなる場面ですよね。
そのため、地位併存説をとる立場においても、無権代理人の追認拒絶は、信義則に反し許されないとする見解が有力になっています。
なお、判例も上記のような場面において無権代理人が追認を拒絶するのは、信義則により制限されると解しています(大判昭和17年2月25日参照)。
信義則の適用は、あくまで個別事件に応じてケースバイケースで判断されます。
たとえば、無権代理行為がなされた時点において、相手方が無権代理であることを知っていたような場合にまで、無権代理人の追認拒絶を信義則で否定して、相手方の保護を図るべきか否かは、ちょっと考えものです。
無権代理人が本人の後見人に就任した場合において、無権代理人が本人のために追認を拒絶できるか、という類似論点があります。
判例において、信義則上、無権代理人は追認を拒絶できない、としたものがありますが(最判昭和47年2月28日)、制限行為能力者保護のために、判例の結論に反対する立場も有力です。
②無権代理人が、追認拒絶をした本人を相続した場合
では、次に、無権代理人が相続をする前に、本人が追認を拒絶していた、という場面を考えてみましょう。
この場合は、地位融合説・地位併存説にかかわらず、本人の追認拒絶によって、無権代理行為の無効が確定していますので、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効なものとはなりません。
もちろん、個別の事情によっては、無権代理人が本人の追認拒絶の意思表示の効力を援用することが、信義則に反する、といえることもあるかもしれません。
しかし、この場面においては、相手方の立場においても、本人の追認拒絶により、無権代理行為が有効になることをすでに期待しえなくなっていました。
そうだとすれば、無権代理人の主張を信義則によって制限するのは、相続前より、相手方を有利にするものです。
そのため、一般的には、この場面において、信義則を適用して主張制限をすべきとまでは考えられていません。
③第三者が無権代理人を相続し、その上でさらに本人を相続した場合
この場合、第三者が無権代理人の地位を相続し、その上で本人を相続しているのですから、理屈としては、無権代理人が本人を相続した場面と同一です。
そのため、地位併存説の立場においても、無権代理人が追認を拒絶するのは、信義則に反すると解する見解が有力です。
ただ、繰り返しになりますが、信義則の適用は、あくまで個別ケースごとに判断されます。
また、この場面では、無権代理行為を行った当事者自身ではない第三者が追認拒絶をすることは、必ずしも信義則に反するものではない、という立論も十分になりたちます
他の相続人との共同相続
最後に、無権代理人がほかの相続人とともに、本人を相続したケースを考えてみます。
たとえば無権代理人Aが、本人BをCとともに相続したという場面です。
この場面においては、Aの利害だけでなく、Cの利害も考えなければなりません。
この点に関し、判例は、追認権がA及びCに不可分に帰属することを根拠に、無権代理行為は、無権代理人Aの相続分についても当然に有効となるものではない、としています(最判平成5年1月21日)
ただ、Cが追認をしている場合には、無権代理行為を有効としてもCの利益は害されませんし、この場合において、Bの追認拒絶を認めるのは、信義に反します。
そこで、上記判例も、ほかの共同相続人が追認をしているときに、無権代理人が追認を拒絶するのは、信義則上、許されないとしています。