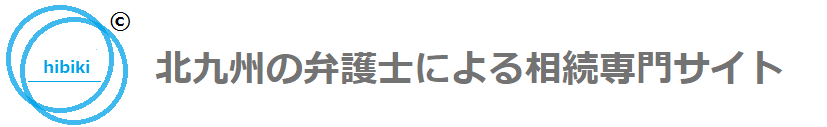今日は、胎児の相続についてです。
普通、子供への相続というと、生きている子供・出生している子供が相続人となります。では、例えば父親が他界した時点において、子供がまだ出生していなかった場合、その子供に相続権はあるのでしょうか。
結論からいうと、相続権は肯定されます。
同時存在の原則
相続法では、通常、相続人は被相続人が亡くなった瞬間からその財産を引き継ぐ「同時存在の原則」が働きます。
これは、相続人となる者は、被相続人が生きているうちに存在しなければならないという原則です。言い換えれば、被相続人が亡くなった瞬間に相続人が存在しない場合、相続が行われないということです。
ただ、これを厳格に貫くと、胎児は、まだ出生していないので、一人の人格として存在しているとの扱いにならず、相続ができないことになります。
民法886条1項
しかし、同じく血縁関係にある相続人と、いまだ出生していないというだけで(胎児の状態にあるというだけで)、相続ができるかできないかが決まるというのは、同じ兄弟姉妹の扱いとして不公平です。
そこで、民法は胎児の相続に関して特別の規定を置いています。
民法第886条第1項 「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」
この規定のおかげで、胎児も相続について、「既に生まれたもの」とみなされる結果、被相続人と胎児とは同時に存在した、との扱いとなり、胎児にも相続権が認められます。
戸籍に記載がない
弁護士が相続人をチェックする場合、戸籍に基づいて、相続関係を把握するのが一般的です。しかし、胎児については戸籍に記載がないため、戸籍の取得によっては把握できません。
また、胎児の権利能力は、弁護士としても、弁護士業として、10年に一度扱うかどうかというレベルの問題ですので盲点となりがちです。書類上だけでなく、日常的な事情の確認が重要となります。
、
学説の対立
教科書的な論点として、この規定をめぐって二つの解釈が対立しています。停止条件説と解除条件説です。
停止条件説: この解釈では、胎児自体は相続権を持っていないとされます。代わりに、胎児は生まれて初めて相続権が発生します。
解除条件説: この解釈では、胎児自体に相続に関する権利を認め、死んで生まれた場合、相続開始時に遡って権利が無効とされます。この説に立つ場合、出生の前から権利が存在するため、胎児に代理人をつけることが可能です。
日本の判例は停止条件説に立つと言われています。
死産の場合
最後に、胎児が死産となった場合、相続法においては胎児は存在しなかったことと見なされます(停止条件説)。