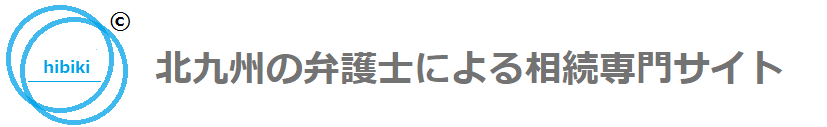今回のテーマは法定地上権です。
資格試験の勉強においても重要なテーマの一つです。各種試験対策では、覚えなければならない判例も少なくありません。
また、実際上も、ケースによっては、実生活にも大きな影響を有するテーマの一つでもあります。
以下、この記事では、定義、内容、要件について解説します。
法定地上権とは
この権利の理解のためのポイントの一つは、「法律上当然に成立する」という点です。
単なる「地上権」が当事者間の「合意」によって成立する約定用益物権であるのに対して、法定地上権は、当事者間の合意に関わらず成立する権利となります。
ここで条文を見ておきます。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
権利の性質・特徴を理解するため、以下、単なる「地上権」との対比を見ておきましょう。
地上権(民法265条)について
地上権というのは、地上権とは、工作物又は竹木を所有するため、他人の土地を使用する物権をさします。
平たく言えば、AさんがBさんの土地を排他的に利用するための権利です。
この地上権を有する者は、他人が所有している土地の上に建物など構築したり、林業等を営んだりすることができます。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
そして、この地上権は、当事者の合意で発生します。
上記例で言えば、AさんがBさんに地上権を設定する、と約定することで成立します。
法定地上権について
他方で、法定地上権は、上記のとおり、一定の要件の下で、その土地上の建物のために、法律上当然に成立します。
条件さえ満たせば、本人たちの合意に関わらず成立します。
この点に、民法265条以下が定める地上権と決定的な差があります。
制度趣旨
考えてみれば、当事者の合意なく、法律で当然に地上権が成立するとした場合、土地の所有者にとって大きな負担が生じます。
そうだとすれば、それ相応の反対利益がないと、制度設計としてはおかしいはずです。
では、どうしてこのような制度が認められているのでしょうか。
一言で言えば、抵当権の実行によって、そこに存在した建物を取り壊さなくなってしまうという社会経済的な損失を防止する、という点にあります
後で述べる「要件」論とも関連しますが、もう少し制度趣旨を見ておきましょう。
土地に抵当権が設定されたケース
ケースとして、まず、次のケースを考えてみます。
土地甲及び同土地上の建物を所有しているAさんが土地に抵当権を設定したところ、その抵当権が実行されて、土地甲の所有権を失った。
.png)
この場合、Aさんは、土地上に建物を維持しておくための土地所有権を失う結果(下図において、土地所有権がBさんに帰属する結果)、本来であれば、建物を取り壊さなくてはいけなくなります(そうしないと、新たな土地所有者に対する占有侵害が継続する)。
しかし、抵当権が実行された結果として、当然に建物を壊さなければならないとすると、本人にとっても、社会にとっても経済的な損失が大きく、合理的ではありません。
建物に抵当権が設定されたケース
上記は、土地に設定された抵当権が実行されたケースですが、建物のみに抵当権が設定されたケースでも同様の問題が生じます。
たとえば、土地甲及び同土地上の建物を所有しているAさんがその建物に抵当権を設定したところ、その抵当権が実行されたというケースを考えてみましょう。
.png)
この場合、抵当権実行に係る競売によって、建物をBさんが取得したとしても、Bさんには土地の利用権がありません。
その結果、仮に競売が成立したとしても、Bは、せっかく手にした当該建物を取り壊さなくなくてはならなくなります。
また、現実的には、こうした仕組みの下では、その建物に買い手はつかないでしょう。
社会経済的な損失を防止
土地と建物の所有者が同じだったのに、競売の結果として、土地と建物の所有者が分かれてしまう、というケースでは上記のような不都合が生じます。
抵当権が土地に設定された場合であれ、建物に設定された場合であれ、当該建物がその土地上に存立する根拠がないとの結果となるのです。
これは、本人にとっても社会的経済的にも損失です。
そこで、このような場合に備えて、民法は、法定地上権という権利を定め、Aさんに土地の利用を許すこととしたのです。
なお、もともと、土地と建物の所有者が同じだったのに、競売の結果として、土地と建物の所有者が分かれてしまう、というケースは、抵当権実行の場面だけに限らません。
単純な強制執行や、租税滞納による公売、仮登記担保権の実行の場面でも生じます。日本では、自分の土地に自分のために借地権を設定する(自己借地権を設定する)ということがないため、こうしたケースが往々にして発生するのです。
このような場合に備えて、民法以外の法典においても、同種の仕組み(建物所有者に土地の利用を許す仕組み)が設けられています。
権利の内容
次に、法定地上権の権利の内容を見ておきます。
存続期間=基本的に協議によるが、協議が整わない場合は30年
地代=基本的に協議によるが、協議が整わない場合、裁判所が定める。
対抗要件=登記が必要だが、借地借家法により法定地上権の対抗要件は建物登記で足りる。
以下、権利の内容につき、土地甲及び同土地上の建物を所有しているAさんが土地に抵当権を設定したところ、その抵当権が実行されて、Bがこれを買い受けた、というケースを念頭にみていきます。
再掲
-1.png)
存続期間
【権利の発生時期】
法定地上権は、競売によって、抵当目的物の所有権が買受人に移転したときに発生します。
上記例では、Bが競売代金を納付したときに、土地所有権がBに移転すると同時に、建物所有者Aのために法定地上権が発生します。
【協議/裁判所が決める】
この場合において、成立した法定地上権がいつまで成立するか、裏を返せば、Bさんは、Aさんの土地利用をいつまで許容しなければならないか、というのが存続期間の問題です。
結論として、これは当事者の協議によって定めることになります。AさんとBさんとの間で何年法定地上権を存続させるかを決めるのです。
もっとも、通常、Aさんにとっては、法定地上権の存続期間が長ければ長いほど、建物を維持できる、というメリットがあります。
他方で、Bさんにとっては存続期間が短ければ短いほど、土地を自分のために早くできるようになる、というメリットがあります。
地代をいくらとするかとも関連する交渉事になりますが、ここでは、互いの利益が相対し得るので、当事者間で協議後が整わないことも少なくありません。
こうした場合、借地借家法という法律で、存続期間は、借地借家法3条により30年になる、と解されています。
↓
同3条が、借地権の存続期間は30年とすると定めている。ただし、契約でこれを変更することは可能(同但し書き)
↓
存続期間は協議によって定めるが、定まらないときは30年となる。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。第3条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。※借地借家法2条1号に規定する「建物の所有を目的とする地上権」に法定地上権が含まれる。
ここで、Bさんの立場からすれば、30年も使われるなんてたまったものではない、地代を安くするから、もっと早くに出て行ってよ、などとAさんに持ち掛ける交渉が考えられます。他方で、次に述べる「地代」につき、Bさんにとって良い条件で合意できるなら、30年以上の利用を認めてもよい、との判断にいたることも考えられます。このように、地代と存続期間にかかる交渉は、セットで行うことになるのが一般的です。
地代
当事者の協議によるが、協議が整わない場合、裁判所が定める
法定地上権が成立する場合、土地所有者は土地を建物所有者に使わせてあげるわけですから、土地所有者は、建物所有者(法定地上権者)に地代を請求できます。
上記の例でBさんはAさんに地代を請求できるわけです。この地代の金額は、当事者の協議によって定まることになります。
もっとも、地代の多寡は、当事者の利害に直結しますので、互いの協議が整わないことも少なくありません。
こうした場合、当事者は、裁判所に地代を定めるよう請求できます。この場合、裁判所が地代を定めます。
少し難しい話 対抗要件
法定地上権も物権なので、これを第三者に対抗するためには登記が必要。
もっとも借地借家法という法律の適用により、建物登記があれば足りると理解されています。
少し話題がそれますが、ここで対抗要件の話をします。難しければここは飛ばしてください。
上記の例で、Bさんが土地をCさんに譲渡した場合、所有者Aさんは自分に法定地上権がある、とCさんに主張できるでしょうか。
法定地上権も、物権ですから、いわゆる「登記」が対抗要件となります(民法177条)。したがって、Aさんが法定地上権を第三者に主張するためには、登記が必要です。
もっとも、法定地上権についても、借地借家法10条1項の適用があります。条文の内容はつぎのとおり。
結論として、ここでの登記は、建物登記だけで足りることになります。したがって、Aさんは、土地上の建物の登記を備えることで、法定地上権を第三者に対抗できます。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。【借地借家法10条1項】
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
ここで関連記事を紹介
上記議論を理解するためには、そもそも対抗要件って何?というところから理解する必要があります。
この点については次の記事で解説していますので、ご参照ください。
要件
すでに見た制度趣旨などからも自明な部分もありますが、ここで、法定地上権の成立要件を整理していきます。
① 抵当権設定当時に、建物が存在していること
② 抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一の所有者に帰属していたこと
③ 土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと
④ 競売により土地と建物の所有者が別人に帰属することとなったこと

条文(民法388条)
再度条文を確認しましょう。民法388条です。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
4つの要件
このうち、要件部分を定めているのは、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったとき」という部分です。
そして、「その土地又は建物につき抵当権が設定され」という部分は、「土地と建物双方に抵当権が設定され」た場合を含むと理解されています。
これを前提に、権利成立の要件を整理すると、次の4つに分類されます。
① 抵当権設定当時に、建物が存在していること
② 抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一の所有者に帰属していたこと
③ 土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されたこと
④ 競売により土地と建物の所有者が別人に帰属することとなったこと
※上記の内、③と④は、制度適用場面上、必要性が自明な要件ですが、①②の要件をめぐっては、別記事で解説するように多数の裁判例が集積しています。
本記事の最後に
以上、法定地上権の制度趣旨、権利の内容、要件について見てきました。
本記事で解説した中で、権利の理解のために重要なのは制度趣旨です。
その制度趣旨は、上記の通り、抵当権の実行ないし競売によって、土地と建物の所有権が別々の人に帰属することとなった場合に、抵当権設定者が建物を取り壊さないといけなくなるという社会経済的な損失を防止するという点にあります。
この点だけでも理解できれば、制度理解としては、かなり進んだということができます。
ただ、実は、要件①「抵当権設定当時に、建物が存在していること」と要件②「抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一の所有者に帰属していたこと」については、その解釈をめぐって、多数の判例が集積されています。
そして、その判例の理解は、権利そのもの理解にも関わりますし、資格試験などでもその知識・理解が問われることがあります。また、予想は付くかと思いますが、実は、これを書き出し始めると、解説のため、かなりのボリュームを要します。
基本的な教科書に載っている判例だけでも10個以上の判例があります。
そこで、要件①と②の意味及びこれをめぐる判例については、機会を改めて解説します。
法定地上権についてさらに知りたいという方、判例理解が資格試験に必要という方は、ぜひご参照いただけますと幸いです。